「全国の指導案をシェア」するサイト、元教員が考案"多忙でも授業準備を可能に" 教員の多忙と孤立の打ち手に「共有」の選択肢

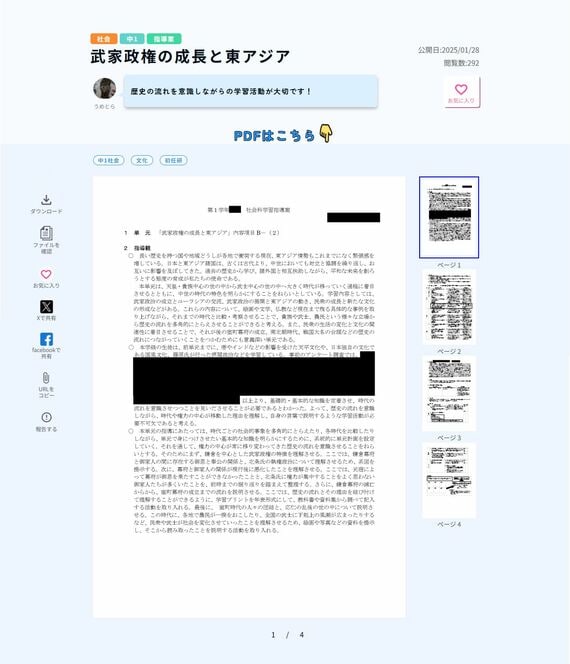
「それでも不安に思う方や、確認作業を煩雑に思う方もいると思います。そこで、サイト内に簡易的な投稿箱を設けて、運営側が責任を持って個人情報などを処理した後に掲載する方法も用意しています」
「せんせい市場」は弁護士の推薦も受けており、投稿自体に収益が発生しないことや、教育公務員特例法が適用されることなどから、投稿に際する法的な問題はクリアしている。また、主な閲覧者は教員なので、そのリテラシーの高さに期待して、報告機能の有効性も見込まれている。今後は「もし、学校で使用する指導案や教材の著作権が自治体に帰属するようになれば、文字通り全国の指導案を共有できるのですが……」と水野氏は本音を漏らす。
こうした教員コミュニティの広がりが、やがて教育界全体の変化につながると展望する水野氏。教員一人ひとりの教室で生まれた創意工夫が、全国に共有され、誰かの学びとなっていく。「せんせい市場」は、いわば教室そのものを拡張する試みへと発展しつつある。
授業は本来、教員と子どもが一番関わる「楽しいもの」
また、新たな試みとして、教室そのものが合わずに苦しむ子どもたちの居場所づくりにも参画しているという。
「発達障害のある子どもたちが、自分に合った学び方で力を伸ばせるような支援もしたいと思っています。現在、支援現場と連携しながら、子どもたちそれぞれの認知特性に応じた学習支援のあり方を検討中です。いずれは無償で通える教室というかたちで、居場所を届けたいと考えています。
挑戦は始まったばかりですが、『授業』は先生と子どもたちが一番関わる場であり、本来とても面白いものです。そう思える先生が1人でも増えてくれたら嬉しいですね。そして1人でも多くの子どもたちが、強制されて授業を受けるのではなく、学ぶことを楽しいと思うことができれば、と願っています」
水野氏は「せんせい市場」について、「実は自分のサイト自体にこだわりはなくて、今後買収されたとしても、まったく別の優れた仕組みがつくられたとしても、それで良いと思っているんです。教員と子どもたちのために、何かしらの波紋を生むことが私の使命です」と語った。
教員が当たり前に楽しい授業を展開できる未来。そしてどんな子どもたちも、当たり前に楽しく授業を受けられる未来。水野氏の視線の先には、学校の内外を問わずどこにでも開かれた「学びの場」がある、そんな世界が広がっている。
「せんせい市場」を見る
(文:末吉陽子、注記のない写真:水野氏提供)
東洋経済education × ICT編集部
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら






























