"いい先生にしか務まらない学校"に疑問、「宿題・テスト・通知表」廃止を校長の挑戦 業務分掌や学年人事も見直し、常識を覆す改革
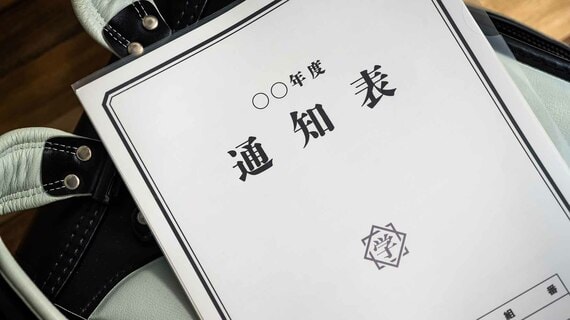
授業を創意工夫しても、結局は「テストで評価」に疑問
長井校長は、東京学芸大学で小学校課程を修了し、東京都江戸川区で教員としてキャリアをスタート。上越教育大学への派遣を経て、府中市教育委員会事務局の専門職員として学校教育の指導・助言を行う指導主事を務めるなど、長らく教育現場と行政の橋渡しを担ってきた。その後は副校長、統括指導主事、校長を経験し、東京都清瀬市で指導課長に従事。2020年、西新宿小学校に校長として着任した。

新宿区立西新宿小学校 校長
東京都公立学校教員、指導主事などを経て、新宿区立西新宿小学校校長に就任。子どもたちの可能性を最大限に引き出すことに情熱を注ぎ、2023年度からは宿題、単元テスト、通知表を廃止するなど、大胆な学校改革を推進。専門は学校経営、理科教育。子どもたちの「学びたい」を育む教育を目指している
(写真は本人提供)
本格的な教育改革に踏み切ったのは、コロナ禍が落ち着きを見せた2023年のこと。長井校長は当時をこう振り返る。
「最初に着手したのは、通知表と単元テスト(小学2年生以上)の廃止です。さらに宿題も見直し、夏休みや冬休みの宿題は廃止しました。日常の宿題も、『漢字を20回書かせる』などの定型的な内容は避けて、子どもが学びたい内容を深められるような、自由度の高い内容に変えました」
画一的な教育の枠組みを見直し、主体的な学びを重視する新しいアプローチを提示した長井校長。子どもたちが自由に、そして深く学べる環境を整えようとするその姿勢は、教育界から注目を浴びた。公立校では他に類を見ない改革に取り組んだ背景には、長井校長がかねて抱いていた違和感があったという。
「教員がどれだけ創意工夫を凝らして授業をしても、最終的な成績は業者が作ったテストで決まることが疑問でした。子どもたちがせっかく楽しく学んでも、最後には『これを分かっているか/覚えているか』が試される。ただ、テストは私費で購入していた手前、使わざるを得ない事情もありました」






























