エヌビディアも手がける「フィジカルAI」の現在地。工場・家庭向け人型ロボット、実現間近の自動運転
また米アップルのロボット研究は興味深く、ロボットが単純にタスクをこなすのではなく、人に対して共感や感情を示すような振る舞いをすることで、ロボットに対する人間側の関与度や好感度が大幅に向上するという。ロボットが人間社会に受け入れられるための重要な要素になるだろう。
フィジカルAIのもう1つの柱である自動運転も、社会実装が進んでいる。米国のサンフランシスコではグーグルの兄弟会社であるウェイモが完全無人のロボタクシーサービスを展開しており、もはや試験段階を超え、市民の足として定着しつつある。実際、同市におけるライドシェアの市場シェアはウーバーが55%を占め、リフトとウェイモがそれぞれ22%で並んでいるとのデータもある。
自動運転はほぼ実現段階
テスラも自動運転分野で先行している。同社の運転支援機能・フルセルフドライビング(FSD)は部分的な自動運転のレベル2と位置づけられるが、ユーザーの体感として自動運転はほぼ実現しているといえる。私自身テスラ車に乗って、家からオフィスまでの行き帰りを含め、一般道でも運転の多くをFSDに任せるようになった。手放しした状態で右左折や合流、一時停止などの動作をFSDがこなしてくれる。テスラは、26年にハンドルやペダルのない完全自動運転車「サイバーキャブ」の生産を開始すると発表しており、FSDで培った物理空間の認識技術などを自社の人型ロボットOptimusに生かしていくだろう。

かつてのロボットブームとの違いは、従来はハードウェアの品質重視だったのに対し、今回はAIが進化の主導権を握っていることだ。ロボット大国と呼ばれた日本の企業の名前が聞かれないのは寂しいが、フィジカルAIはまだ黎明期だ。制御技術やセンシング、耐久性に加え、物理空間データの不足など技術的な課題も多く、コストや社会的受容性など課題を挙げるときりがない。実用化に至るまでの道は依然として長く険しい。
それでも、労働力不足や交通問題を解決するフィジカルAIが秘める可能性は計り知れない。街にロボットがあふれ自動運転の車が行き交う光景は、まさに私たちがかつてSF映画などで夢見た未来そのもの。AIの力によって、それがいま現実に近づこうとしている。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら














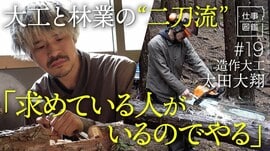






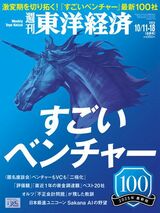









無料会員登録はこちら
ログインはこちら