「赤いきつねCM」露出ないのに"性的"と炎上のワケ 日清食品「どん兵衛」の"擬人化CM"は許されたが…
ただし、これまでは肌の露出が多かったり、女性の身体的特徴が過度に強調されたりしているものが大半だった。今回の「赤いきつね」のケースはそうした事例とは異なっている。
企業側も、性的な表現が炎上しやすくなっていることは重々理解しており、細心の注意を払うようになっている。


「性的な表現」は効果よりもリスクが高い
1990年代くらいまでは、他の日本企業と同様、広告業界も男性中心の社会で、女性の管理職はごく少数だった。そのため、広告表現も男性目線になりがちな傾向も確かにあった。さらにその頃は、家計の収入源も男性のウエイトが高く、商品購入の意思決定も、男性の関与度が高かった。
そうした時代においては、広告に性的な表現を盛り込むことは、一定の効果があったといえるだろう。
『メディア・セックス』という書籍が、1989年に日本語訳版が発行され、ベストセラーになったことがあった。本書の中では、企業が広告の中に性的な表現を埋め込むことで、消費者の潜在意識に働きかけ、購買意欲を喚起しているという主張がされている。
「性的イメージの刷り込みによって、消費者はマインドコントロールされている」というのは刺激的な説ではあったが、本書はいまでは「トンデモ本」の類いとして位置づけられており、この説は受け入れられてはいない。
広告業界で長らく働いてきた筆者の体験からしても、そんなに容易にマインドコントロールできるほど、消費者は単純ではない。
表現規制が厳しくなっており、不適切な表現が炎上しやすくなっている現在では、意図的に広告に性的な表現を含ませることは、効果よりもリスクのほうが高い。
今回の「赤いきつね」のアニメ動画ついては、性的な表現をするつもりはなく、意図せずに批判を浴びてしまった――というのが実際のところだろう。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
















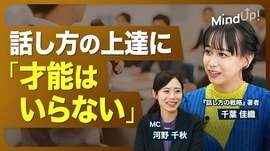





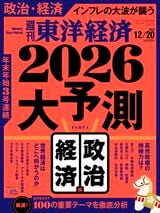









無料会員登録はこちら
ログインはこちら