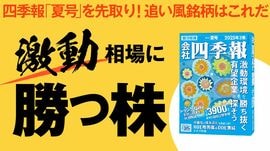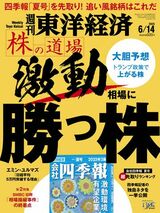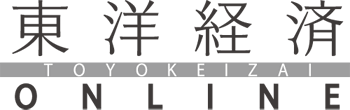子のしつけ「厳しく」と「のびのび」決定的な学力差 子が取り組む課題は「MUST・CAN・WANT」に分ける
たとえば子どもが昆虫に関心を持っていたら、本棚に昆虫の本を忍ばせておきます。そして子どもがその本を引っ張り出して読んだら、「昆虫の本を読んでいるんだ、すごいね!」と褒める。すると子どもは喜んで、「もっと読みたい」「もっと知りたい」というWANTが生まれるのです。
CANが増えるたびに褒められると学ぶのが楽しくなり、「勉強したい!」というWANTが育っていく、というメカニズムです。
MUSTに根拠はいらない
この、MUST→CAN→WANTの順番は、大人を動かすときにも同じことが言えます。
ビジネスの現場でも強い組織は、MUST基準が高いのです。
たとえば飲食店で言えば、お客様が入店した際に、「元気で明るい、ウェルカム感あふれる挨拶をする」というのは、とても大切なことです。入店時のお出迎えの印象で、お客様の満足度も大きく変わりますし、リピート率にも影響します。うちのお出迎えは、こういう声の大きさで、こういう表情で、こういうしぐさでウェルカム感を表現するのだ、というMUSTを教え、新人にも徹底させられているお店のサービスレベルは高くなります。
ここでこのMUSTに根拠はいりません。ただ従ってもらうのです。無理やり理由付けしようとしても、最近は理屈をこねることに長けている人もいますから、「私は挨拶をする意味がわかりません」「私はそんな挨拶をされたらイヤです」とかいろいろ言われてしまいます。
子どものしつけも同様で、家族のMUSTは夫婦で合意していれば、根拠なく求めて問題ありません。
朝何時に起きるかとか、人と会ったら挨拶するとか、お小遣いはいくらかとか、YouTubeを1日何時間見ていいのかとか、携帯電話を持つかどうかとか、塾に行くのかどうかとか、夫婦で決めて、強引に「うちはうち、よそはよそ」とします。根拠を付けようとしても埒があきません。「うちのルールはそうなんだ」とMUST基準として伝えることが重要です。