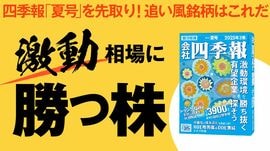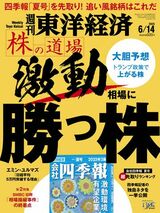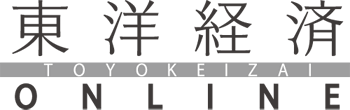子のしつけ「厳しく」と「のびのび」決定的な学力差 子が取り組む課題は「MUST・CAN・WANT」に分ける
そのうえで、MUST基準を守れていたら、他のことはどんどん褒める。CANを増やす。そうすると、子どものWANTが育っていくのです。
我が家で成功した、ワンパターンの教育法
我が家で最初に子どもの関心を引いたのは、電車でした。
電車が通るのを見るたびに指をさして「ピンクの電車」とか「みどりの電車」と嬉しそうに報告してくれるので、私たちは、学んだ通り、本棚に図鑑を忍ばせたりしてみました。
すると息子は自ら図鑑を引っ張り出し、読み始めたので、シメシメとばかり、「すごいね!」と褒めると、喜んでさらに熱中して読み込んでいました。電車の絵本を読み聞かせしたり、トイレに路線図を貼ったり、実際に電車に乗ったり乗り換えたりしていました。
やがて、山手線、東急東横線などの路線の名前を覚え始め、特急とか新幹線とか、どんどん関心が広がっていきました。
私と息子で路線の名前を交互に言って思いつかなくなったほうが負けのゲームをしたり、あいうえお順に「あ」から始まる電車とか駅名を言うクイズをして、「阿蘇ボーイ (特急の名前)」、「明石駅」とか答えているうちに、4歳のときにはひらがなもカタカナを読めるようになり、小学校に入るころには漢字もだいぶ読めるようになっていました。
時刻表にも興味が出て時計が読めたり、新幹線は時速340キロが出るとか数字にも興味を持って足し算とか引き算が得意になっていました。「好きなことって人の成長を促すのだな」と何度も驚かされました。
次に、恐竜が好きになったときも同じように、恐竜の図鑑を本棚に忍ばせ、自ら図鑑を引っ張り出したのを褒めていたところ、まんまと恐竜の名前に詳しくなりました。「アロサウルスはジュラ紀で、ティラノサウルスは白亜紀だから、同じ時代にはいなかったんだ」とか、「ブラキオサウルスの体長は何メートルだ」とか解説してくれるようになりました。