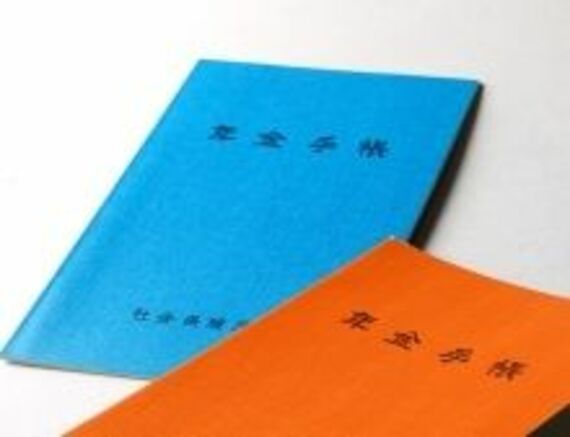みんなが「得を感じられる」政策こそが必要だ!--行動経済学からみた年金問題の解決法
年金問題は、再び政策論争の焦点となっている。過去よりも、より現実的に何らかの政策変更が行われそうだと思われていたが、結局、政府・民主党は踏み込んだ改革案に突っ込むことができず、中途半端な議論に終わる可能性が高まってきた。年金問題は政治的に解決が最も難しい問題の一つだと一般に思われているとおり、今回も本質的な改革に失敗し、破綻へ向かっていくのだろうか。
しかし、いったい年金問題というのは、本当に難しいのだろうか。答えは、ノーである。理論的にはこれほど単純な問題はない。それなのに、なぜ解決が難しいのか。ここでは、行動経済学的な考え方で議論してみたい。
多くの政策論者は、年金の本質をわかっていない。あるいはわかっていても無視している。年金とは、お金のやりとりを人々の間でしているだけのことなのである。これほど単純なものはない。カネを移すべき対象とタイミングを適切に選び、適切なタイミングで、他の人から移転する財源を得るということに尽きる。
なぜ単純なのに解決できないのか。それは単純すぎるからである。制度を変えれば、誰かが得をして、誰かが損をする。そして、年金の場合はそれが誰の目にも明らかだから、みんなが得をしない限り、損を被る人々は強烈に反対する。だから、必ず猛反対が起きる。
プロスペクト理論によれば、得と損では、損のほうを人々は圧倒的に強く感じる。また、絶対水準ではなく、変化から幸福と不幸を感じる。だから、10得をする人が10人生まれ、10損をする人が10人生まれれば、前者の人は黙っていて、後者の人は声を上げるから、反対ばかり聞こえる、という問題がでてくる。
実際には、10損するとは20不幸が増えたように感じられ、10得することは8ぐらいにしか感じられないから、その非対称性から、損得相殺されるような改革案は通らないだけでなく、実際に人々を不幸にするのである。