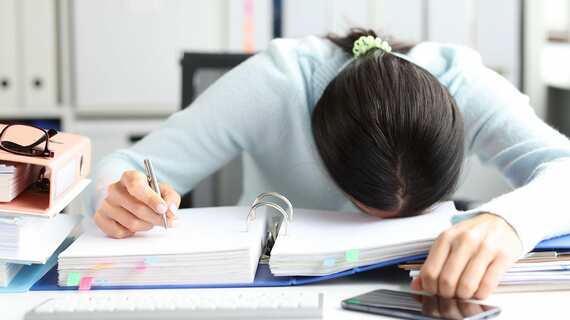
「どうして学校の先生はこんなにも忙しくなったのか?」
「一昔前までは授業で使うプリントもテストも全部手書き。印刷にも時間がかかった。今は電子化され、ICTもそれなりには使われているのに、なぜ忙しいままなのか?」
こういう質問を、たまにマスコミの方から受けることがある。現役の教職員からも似た質問が来ることさえある。学校の多忙の背景、原因は単純なものではないので、端的に答えるのは難しいが、ここでは根拠を基に、なるべくわかりやすく解説してみたい。

教育研究家、一般社団法人ライフ&ワーク代表
徳島県出身。野村総合研究所を経て、2016年に独立。全国各地の教育現場を訪れて講演、研修、コンサルティングなどを手がけている。学校業務改善アドバイザー(文部科学省委嘱のほか、埼玉県、横浜市、高知県等)、中央教育審議会「学校における働き方改革特別部会」委員、スポーツ庁、文化庁において、部活動のあり方に関するガイドラインをつくる有識者会議の委員も務めた。Yahoo!ニュースオーサー。主な著書に『校長先生、教頭先生、そのお悩み解決できます!』『先生を、死なせない。』(ともに教育開発研究所)、『教師崩壊』『教師と学校の失敗学』(ともにPHP)、『学校をおもしろくする思考法』『変わる学校、変わらない学校』(ともに学事出版)など多数。5人の子育て中
(写真は本人提供)
先生の働き方は変わったか?
少し前に定年退職した元校長らからは、次のような話もよく聞く。
「私の若い頃は、放課後に職員バレーをしたり、仕事が終わった後スキーに行ったりと、職場にゆとりがあった」
「土曜に授業があった時代のほうが、今よりはるかに時間の流れがゆったりしていたように思う。先生たち同士もよく相談したり、雑談したりしていた。今はもう、みんなパソコンに向かってしゃにむに仕事を終わらせようとしている」
人間の記憶は美化されやすいことが科学的にもわかっているらしいが、こうした声を単なる思い出話として片付けるのはどうかと思う。今後の教職員の働き方を考える真理の一端、ヒントがあるように思うからだ。
ここ5~6年で学校の働き方改革は、それなりには進んだ(後で述べるとおり問題も多いが)。少し前までは6.1%の市区町村しかタイムカードなどによる出退勤の管理をしておらず(文科省「平成28年度教育委員会における学校の業務改善のための取組状況調査」)、多くの自治体が出勤簿にハンコを押すだけというお粗末な状況であった。「労務管理」という概念は、公立学校にはほとんどなかった、と言ってもいいだろう。































無料会員登録はこちら
ログインはこちら