北海道「並行在来線」貨物存続に立ちはだかる難題 費用と複雑な「支線」の扱いで議論紛糾の可能性
函館本線は、函館から七飯までの約14kmは複線だが、七飯―大沼間(約13km)は西側の本線と東側の通称「藤城支線」に分岐する(それぞれ単線)。また、大沼―森間も西側の本線(約22km)と海沿いの通称「砂原支線」(約35km)に分岐している。

砂原支線はもともと渡島海岸鉄道という小さな鉄道会社が1928年に敷設し、1945年に国有化された。藤城支線は、本線の勾配を避けるルートとして1966年に国鉄が建設した。
現在、貨物列車は急な上り勾配を避けるため、上り列車は砂原支線、下り列車は藤城支線を走行している。砂原支線には駅が6つあり、普通旅客列車も1日上下12本走行している。
一方、藤城支線には駅がなく、旅客は1日に普通列車が下り3本走っているだけだ。かつては特急列車も走っていたが、北海道新幹線との接続駅である新函館北斗駅(旧渡島大野駅)が西側の本線にあるため、旅客列車の主要ルートからは外れた。
地元は藤城支線を引き継がない前提
沿線自治体はこれまでの協議で、函館と新函館北斗(約18km)を結ぶ新幹線リレー列車「はこだてライナー」は存続させたい意向だが、それ以外の区間の維持を担うことには難色を示している。
国交省幹部は「まずは地元で旅客列車の運行範囲や形態を決めてもらう必要がある」と話す。貨物路線として維持するにしても、地元が残したい旅客路線の形が定まらなければ具体論には入れないからだ。
道は、ほとんど貨物列車しか走らない藤城支線はJRから引き継がない前提だ。一方、砂原支線は高校に通学する生徒の利用も多く、大沼―長万部間には一定数の乗客もいるため、2023年内にも開かれる次の地元協議会で旅客列車の走行範囲を詰めていく方針。ただ、4月に当選した函館市の大泉潤市長は新幹線の函館駅乗り入れを目指しており、函館―
函館―長万部間の路線をすべて残した場合、道は30年間で約817億円の赤字が出ると試算している。藤城支線を外しても、それ以外の全区間を旅客路線として第三セクターが運営すれば、地元負担は重くなる。三セクへの補助金にあたる「貨物調整金」も2030年度以降の財源がおぼつかないという事情もある。




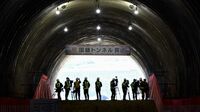




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら