インフレに「強い業種」「弱い業種」の意外な実態 統計的手法で「上がる業種」「下がる業種」を抽出

総務省から2月24日に発表された1月の消費者物価指数では、生鮮食品を除く総合指数が前年同月比(前年比)で4.2%上昇しました。第2次石油危機のあった1981年9月(2020年基準で4.3%)以来、41年4カ月ぶりの物価上昇です。
政府が1月から実施している電気・ガス代の補助金制度などの効果もあって、今後は物価高のスピードは緩むと見られます。しかし各種の報告によると、企業が製品を作る際の原材料の価格上昇した分を製品価格に上乗せ(価格転嫁)できていない企業が多いため、今後も価格転嫁の流れから物価上昇が進むと見られます。
物価が“継続的”に上昇する状態はインフレ(インフレーション)と呼ばれます。インフレでモノの値段が上がることは、モノを買うのに必要なお金が増えることです。お金の面から見ると、お金の価値が下がるということです。ですから、インフレ時には、何もしないで自宅に現金を置いておくタンス預金をしておくと、物価上昇分、ちょうど現金の価値が目減りしてしまいます。銀行で定期預金でも、依然として低い利率ですから物価の上昇を補う利息とまではいきません。
それでは、インフレ時にはどのような資産で貯蓄や投資をしたらよいのでしょうか。実は、伝統的に株式投資はインフレに強いと言われています。今回は株式が本当に“インフレに強い”のか、そしてインフレに強い業界はどこかを探ってみました。
物価と株価はどう関係している?
まずは、物価と株価の推移から確認しましょう。下図は、生鮮食品を除いた消費者物価指数(青グラフ)と日経平均株価(赤グラフ)の推移を見たものです。

私たちが買うモノやサービスの値段の動きを見るのに消費者物価指数がよく使われます。特に“生鮮食品を除いた”指数が注目されます。これは、雨量や日照量で収穫が大きく影響される野菜などは値段の変動が大きいことから、生鮮食品を含めて物価の動きを見てしまうと、物価が“継続的”に上昇しているか、つまりインフレかどうかの判断がわかりにくくなってしまうからです。

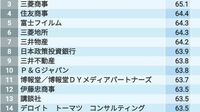
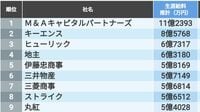

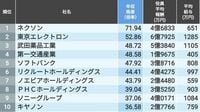



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら