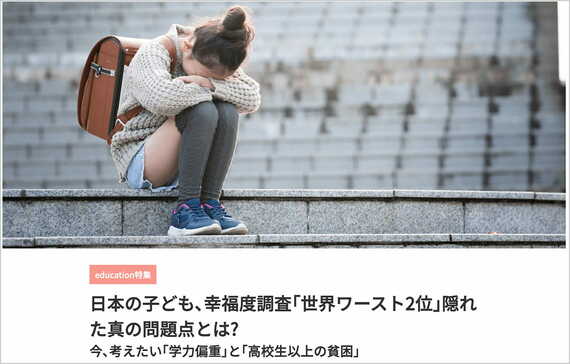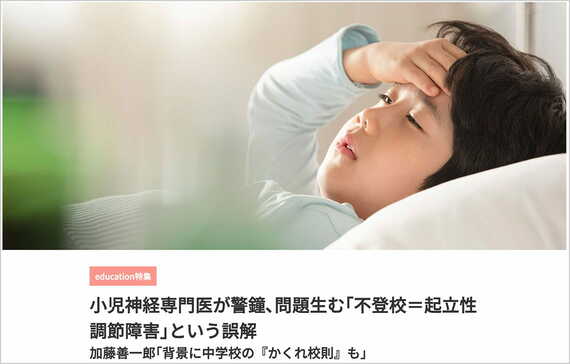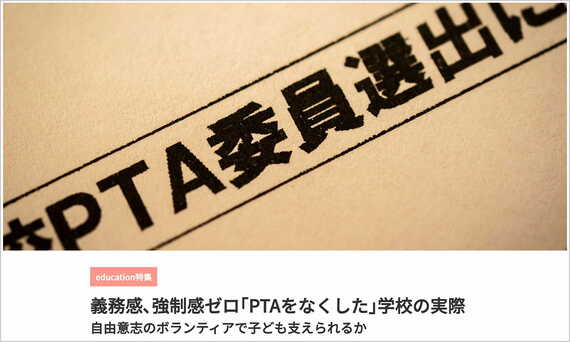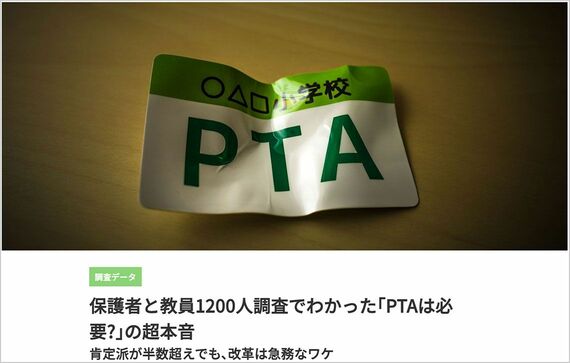保護者向け、2022年がよくわかる「最も読まれた記事」トップ10 中学受験から不登校、ギフテッド、海外進学まで
不登校の児童生徒は24万4940人で過去最多
文部科学省は2022年10月、全国の小中学校で21年度に不登校だった児童生徒は24万4940人と過去最多となったことを公表した。こうした不登校児童生徒への対応も、日本の子どもたちの幸福度を考えるうえで、今までのあり方を見直すべき課題の1つと言えるのではないか。
最近はその一因に「起立性調節障害」という病気があることが知られるようになってきた。一方で、「誤解も生じている」と話すのは、小児神経専門医として不登校の子どもたちの診療に当たる岐阜大学大学院教授の加藤善一郎氏。
「小児神経専門医が警鐘、問題生む『不登校=起立性調節障害』という誤解」では、不登校特例校の岐阜市立草潤中学校で「こころの校医」も務め、講演や著作を通じて起立性調節障害の啓発に取り組む加藤氏に、起立性調節障害から学校に行けなくなっている子どもの現状や、周囲が理解すべきことなどについて聞いている。
従来のPTA組織を廃止し、ボランティア制へ
最後に、定番人気となっているPTAを取り上げた2つの記事を紹介したい。
子どもたちの健やかな成長を目的に保護者と学校、地域が協力し合ってさまざまな活動を行うPTA。コロナ禍で活動の縮小を余儀なくされる一方で、ここ数年で改革に取り組むPTAが増えてきている。
「活動負担が大きい」「義務感、強制感、前例踏襲感が強い」などネガティブな声が聞こえる中、従来の組織を廃止し新たな団体を立ち上げ、すべての会員が義務感を感じることなく活動する学校も少しずつ増えてきているのだ。
「義務感、強制感ゼロ『PTAをなくした』学校の実際」では、2013年度をもってそれまでのPTAを廃止、1年の準備期間を経て15年度からすべての活動を“ボランティア制”で行う「PTO」に生まれ変わった東京都大田区立嶺町小学校を取材した。
「PTAは必要?」保護者と教員1200人に聞いた
PTAは、共働きの家庭が増加する中で、保護者に負担を強いる活動として敬遠される向きは依然として強い。
東洋経済では2021年12 月、保護者と教員それぞれ600名、計1200名にPTAに関する意識調査を行って、その結果を22年3月「保護者と教員1200人調査でわかった『PTAは必要?』の超本音」
で公開している。
PTAの必要性そのものについては、61.5%もの保護者と、54.2%の教員が肯定しているものの、ペーパーレス化やオンライン会議など活動の見直しや効率化を目指すべきといった意見が多いなど、改革が急務であることは結果からも明らかだ。これから改革を進めていくというPTAには、ぜひ参考にしてほしい記事だ。
(注記のない写真:Fast&Slow / PIXTA)
上記記事をまとめ、さらに2023年最新の「子育て」に関する記事も追加した動画はこちらで公開しています。
最新の「子育て」人気記事とは? その他、ギフテッド教育、首都圏の中学受験、PTAのリアルなど話題の記事も動画で紹介
東洋経済education × ICT編集部
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら