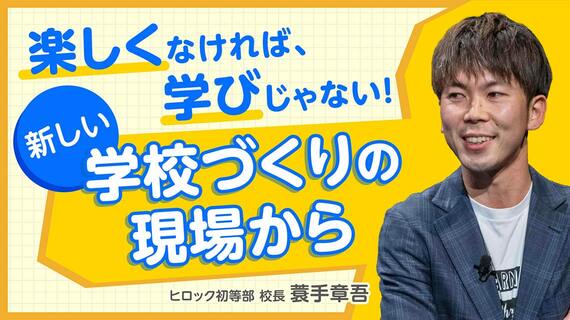そのほうが、よりそれぞれの子どもたちの学びの段階に合わせた課題に対応したり、学習しやすい環境となるのではないでしょうか。前置きが長くなりましたが、このような考えを基に、これまでの一律一斉の学習方法を一変させて実践してきたのが、自由進度学習でした。
子どもそれぞれのペースで学習を進める「自由進度学習」
例えば、ある年担任していた公立小学校の6年生算数の授業を取り上げてみます。子どもたちは、それぞれに自分で「めあて」を書き込み、自分の選んだ座席で学習を進めています。掛け算を九九まで戻って学習している子もいれば、有名私立中学の入試問題を4人で頭を寄せ合って解いている子たち、テストに向けて教え合っている子たち、一人で黙々と高校数学のドリルに取り組む子などさまざまです。

紙のプリントで学習する子もいれば、テクノロジー端末のAIドリル教材に取り組む子、インターネットで問題を探す子もいます。どの子も、誰がすごいとか誰が速いとかいった比較をせず、フラットに応援し合い、リスペクトし合っています。教師は教室を何十周も回りながら、個々の進捗を確認したり、個別の質問に答えたりします。
単元のまとめテストは全員同じタイミングで受けてもらっていますが、その日にちは早めに告知しているので、子どもたちはテストの日を意識しながらそれぞれのペースで学習を進めています。
いかがでしょうか。この自由進度学習、見たことのない方にはイメージしにくいかもしれませんが、全国の公立小学校でも少しずつ取り組む学級や学校が増えてきています。もともと、自由進度学習は大正時代から行われてきた学習方法でした。
しかし、子どもたちの進捗に応じたプリントを準備する煩雑さや学校内外からの要請などから、なかなか実践が広まらなかった背景があります。それがここにきて、1人1台の端末が行き渡ったことにより、多くの学級で選択可能な方法となったわけです。
ここでは、その理念や具体的な方法に触れられなかった点も多くあります。もし「もっと詳しく知りたい」と思ってくださった読者の方がおられましたら、拙著『子どもが自ら学び出す!自由進度学習のはじめかた』も参考にしていただけるとうれしいです。
(注記のない写真:蓑手氏提供)
執筆:蓑手章吾
東洋経済education × ICT編集部
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら