
行動経済学は、パラダイムを引っ繰り返す「革命」を経済学界にもたらしたのか。現在のところ、その答えはノーだ。
「リチャード・セイラー教授は『将来、行動経済学という言葉はなくなる』と話すが、それは経済学が行動経済学の成果を組み入れて再構成されるという意味だ」と甲南大学の筒井義郎特任教授は語る。
経済理論の発展は、数学的解法のブレークスルーとともにあった。たとえば、新古典派の限界効用理論が標準的な経済学の地位を獲得したのも、「制約付き最適化問題」という数学的解法で簡単に答えを導けたことが大きかった。
ロバート・ルーカス氏が主導し、現在のマクロ経済政策に大きな影響を与えている合理的期待形成理論、ジョセフ・スティグリッツ氏らによる情報の経済学(情報の非対称性)なども「数学的解法をどう定式化して解いたらよいかを明らかにした点が画期的だった」と筒井教授は言う。
行動経済学はこの点、伝統的な経済学では説明できない逸脱行為(アノマリー)を実際にある現象として指摘できるものの、それを系統的な理論や数学的解法に発展させることには手間取っている。



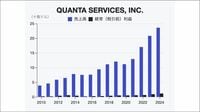





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら