一方、天然痘は人獣共通感染症ではない。天然痘ウイルスは自然の状態ならば人間以外に感染しない。世界保健機関(WHO)が主導する世界的な天然痘撲滅キャンペーンが1980年までに成功を収めることができたのはそのためだ。つまり天然痘ウイルスは人体(あるいは慎重に管理された実験動物)以外で生存・複製する能力が欠けていて、姿を隠すことができないため、根絶することができた。
ところが、人獣共通の病原体は隠れることができる。人獣共通感染症がとても興味深く、複雑で、非常に問題なのはそれが理由だ。
消えたように見えても、どこかに潜んでいる
もちろん、これらの病原体が意識的に隠れているわけではない。過去の偶然の出来事の中での選択の結果、生存と複製の機会を得られたために、今いる場所に棲みつき、成りゆきのままに乗り移っているのである。自然淘汰というダーウィンの冷徹な論理によって、進化は偶然の出来事を戦略として組み込み、体系化する。
それらの中で最も人目につかない戦略が、保有宿主(ほゆうしゅくしゅ)と呼ばれる生き物の中に潜むことである。保有宿主とは、その病原体を運び、慢性的に体内にすまわせながら、ほとんど、あるいはまったく病気にかからない種のことである。
アウトブレイクの合間で病気が姿を消したように見えるときでも、その原因となった病原体がどこかに潜んでいるのは間違いない。地球から姿を消した可能性もなくはないが、おそらくそうではないだろう。その地域で死に絶え、風まかせ、運まかせで、どこかほかの地域から戻ってこない限り、再び現れないかもしれない。あるいは何らかの保有宿主に潜みつつ、今もあたり一帯をうろついている可能性もある。
それは齧歯類だろうか? それとも鳥だろうか? 蝶だろうか? コウモリだろうか?
保有宿主の中に身を隠すことは、生物多様性が豊かで、生態系が比較的保たれている場所であればとても簡単だ。逆もまた真であり、生態系の破壊は病気が現れる原因になる。
木を揺すれば何かが落ちてくる。食べるためにコウモリを捕らえれば、ほかの何かがついてくるかもしれない。家族や村の仲間に振る舞おうとチンパンジーを解体したとき、どんな思いがけない恐怖に襲われるかもしれない。病原体がある種の宿主から別の宿主へ移動するとき、その感染はスピルオーバーと呼ばれている。
さて、ここまでで基本的な概念は身についたはずだ。あとに続く物語のすべての出発点はここにある。――エボラは人獣共通感染症である。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

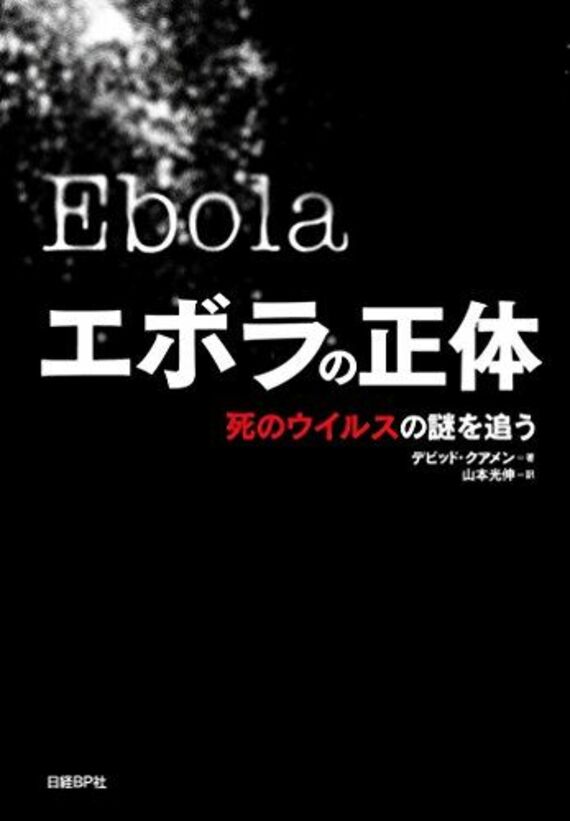






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら