電鉄が「老いる郊外住宅地」を見捨てないワケ 東急と京王が住民とタッグを組んで問題解決

ある日の夕方、東京郊外の「ニュータウン駅」からバスで15分の団地を訪れた。下校途中の中学生と老人が、急坂を上る。食料品や日用品の大きな包みを担いだ老夫婦が、5階建てビルの高さはあろうかという長い階段を降り、谷間の川筋に沿って乱開発された古い建売住宅群に帰っていく。団地の中心にあったはずのスーパー、そば屋、寿司屋は、調剤薬局、デイサービス、鍼灸院に代わっていた。
郊外住宅地は急速に老いている。住宅やインフラの老朽化、商圏の壊滅、高齢者の移動手段の確保などの課題が、未解決のまま山積している。
東急電鉄と横浜市が、連携協定を締結
1960〜1970年代、ほぼ同時期に開発された東急多摩田園都市もまた、誕生から半世紀以上が過ぎた。
「住宅地として環境のよい丘陵部は、高齢者にとっては、逆に『階段や坂が多い』という制約になりえます。加えてライフスタイルの変化で、夫婦共働きが多い現役世代は『職住近接』指向が強く、かつての『憧れの生活』だった郊外戸建住宅が選ばれない傾向にあります。
郊外住宅地を『世代を越えて住めるまち』に変えていかなければならない、という危機感を感じていました」。東急電鉄都市経営戦略室課長補佐の森口雅昭さんはこう語る。
行政にも同じような危機感があった。「まちが老いる」ことはインフラの更新や医療機関の整備などコスト増に直結するが、生産年齢人口は減るので税収は落ち込む一方だからだ。

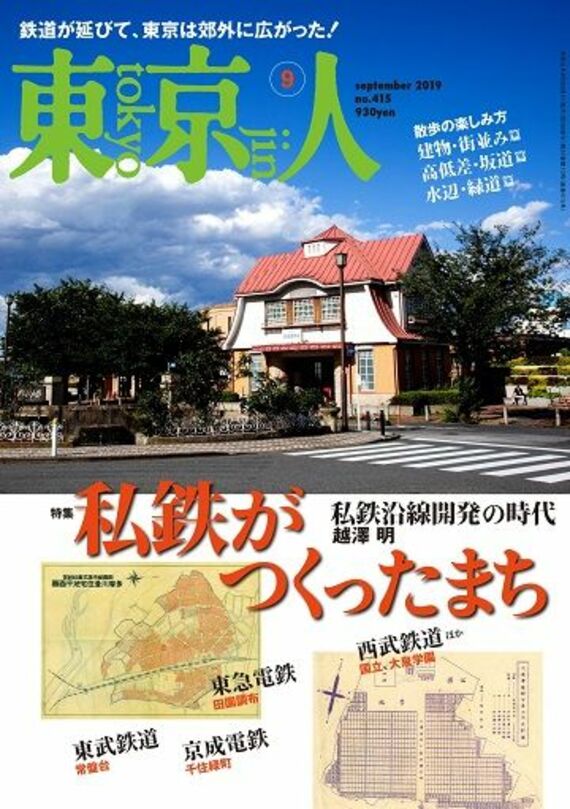

































無料会員登録はこちら
ログインはこちら