ひどい家庭環境で育った日野少年が、いつしか漫画を使い人を呪い殺すようになる。いじめっ子を殺した後は、両親や編集者も呪い殺した。そして漫画の最後に日野青年は読者を指さして、
「こんどは、きみが死ぬ番だ!」
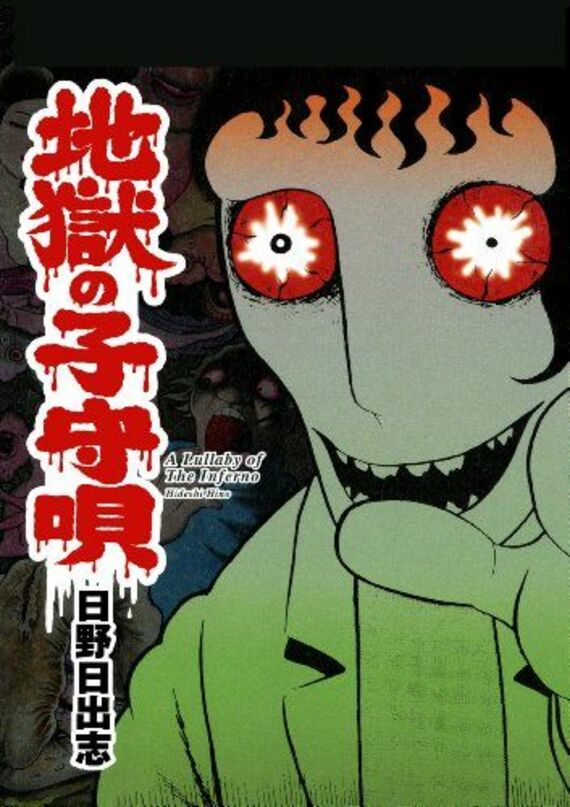
と宣言する。急に漫画がフィクションと現実の境界を超えてきた感覚に、当時の少年たちは怯えた。編集部には「本当に死んじゃうんですか?」という手紙がいっぱい送られてきた。PTAからの苦情も殺到した。
「両親を『最悪の人間だ』と描写したうえで、惨殺してますからね。
『お前はなんてこと描くんだい!! わたしが満州から苦労して連れて帰って来たのは、こんな漫画を描かせるためじゃないよ!!』っておふくろに怒られました。親戚一同にも散々文句を言われましたね。
『漫画なんだからギャグだよ!!』と言い訳したんですが、まったく聞く耳もってもらえなかったです。『蔵六の奇病』が発表された後もPTAなどから非難の嵐が来たんですよ。グロテスクだの残酷だのって。
でも子どもからの手紙を読んだら『蔵六が可愛そうで、抱きしめて寝ました』って書いていました。表面上のグロテスクさじゃなく、蔵六の心の純粋さみたいなのをちゃんと見抜いている。子どもの方がずっときちんと読んでくれているな、って思いました」
日野さんはそもそも杉浦茂のほのぼのとしたタッチの漫画を愛した人だ。怪奇漫画のタッチもそもそもは好きではなかった。
怪奇漫画家という「役」
「蔵六の体に点描を打ってると、だんだん精神が病んでくるんですよ。無理して描いてるんです。何かが怖いんじゃなくて、描いてること自体が怖いんです。夜中に背中がゾワゾワとして電気が走って、体が分解しそうになるんです。
プロになってからは、机に向かうときだけ怪奇漫画家の日野日出志を演じるようになりました。漫画を描く時以外は、日野日出志は捨てて、素の人間に戻りました。そうしないと心も体ももたなかったんですね」
怪奇漫画家というのは100%望んだ結果ではないが、それでも漫画家としてのポジションは確立された。
「遊園地で言えばヒーローショーではなくお化け屋敷みたいな立場ですね。
元野球選手だった八名信夫さんが俳優になった後、悪役ばっかり演じてらっしゃるのを見て、どのような気持ちで演じてらっしゃるんだろう? と想像しました。そしてずいぶん勇気づけられました。
特殊なポジションだけど『やってやるよっ。とことんやってやろうじゃないか!!』って腹をくくりました」
当時は漫画を描きながらも、漫画家同士の交流はほとんどなかったという。
「どうせみんなに嫌われてるんだろうな~と思ってました(笑)。
25~26年前に石ノ森章太郎さんがマンガジャパンという組織を立ち上げました。ストーリー漫画家の団体で、そこに入ってやっとほかの漫画家さんと交流することが増えました」































無料会員登録はこちら
ログインはこちら