香川の離島が「現代アートの聖地」に化けた訳 安藤建築と「3人の芸術家」の融合という難題
理論家の多い建築家の中では、安藤さんはずいぶんと感覚的な部分が強い建築家だ。こんなことを言ったら怒られるかもしれないが、あのコンクリートの厚みは本当に構造上必要なのだろうかと思う。あれはもしかしたら構造の問題ではなく、安藤さんの精神の問題なのではないのかとさえ思う。それに、光と影の扱い方、空間の切り取り方、地勢を借りた場所の読み込み方には、いずれも独特な野性味を感じる。
一言で言えば、安藤建築とは“表現の強い建築”なのだ。あのコンクリートの安藤空間に現れる陰影は際立って心理的である。それを、モネの空間に対峙し、対話するものにしたい。安藤さんには安藤さんの空間に集中してもらい、デ・マリアやタレルにはそれぞれでやってもらう。モネの空間も、僕らが責任を持って考える。
このころになるとさすがに、安藤さんとの間に一定の信頼関係ができあがっているように思った。まあ、秋元は直島の仕事はまじめにやっているし、徹底してやっている、そう思ってくれていたのかもしれない。
作家がやりたいことと、安藤さんのやりたいことがバッティングしたとき、それを調整するのが僕の役割だ。僕が安藤さんに反対するときは、意味もなくただ反対しているわけではなく、作品を最高のかたちで仕上げるためにあえて異を唱えている。そのことを安藤さんは理解してくれている。そう信じなければ前に進めないと思った。とはいえ、徹底的に話し合わなければならないことに変わりはない。
こうした折衝は、安藤さんと直接やりとりすることもあるが、ほとんどは岡野さんとやることになる。この岡野さんがなかなか“うん”とは言ってくれない。安藤さん本人に直接ものを言えない分時間がかかるし、手間である。いくら作家側の意図を伝えたところで、岡野さんは「安藤の建築にそういう手法はありえません」の一言である。たとえばモネ室の角がアール(曲面)に処理されるところや、デ・マリアの天井部分のデザインなどがそうだった。
すると僕は、「そこをなんとか」と言い、両者が成り立つところを探るのである。
どのような世界観で織りなすのかが重要
建築家からすれば、建築の内外ともに建築物である。その中に建築的領域と美術的領域を分けて考えるなどありえなかっただろう。しかし、デ・マリアやタレルのようなインスタレーションの作家は、空間が作品の一部なのだから、建築内部であっても作家が決めていくものだ。作家たちにとっては、そこは作家に任せてほしいと思っている。
絵画であれば、額縁のなかだけで作品を完結させることができる。だが、今回実現しようとしているのはあくまで空間芸術である。つまり、その空間の入り口のドアを開けた瞬間から、そこはその作家の領域でなければならない。
とはいえ、来場するお客さんからしてみれば、どこまでが安藤建築で、どこからがデ・マリアの作品か、などと個別に観るわけではない。1つの連続した空間と時間を体験するのであって、そこで安藤さんを含む4人の作家が、どのような世界観を織りなすのかが重要となる。と同時に、それをどのように連続させていくかが肝になる。それらをうまく融合して一体感を創出することが求められる。
映画にたとえればわかりやすいかもしれない。映画では、複数の俳優がそれぞれの個性を発揮しながらいい演技をし、キャラクターの違いを際立たせたうえで1つの映画作品として上質のものに仕上げる。これとよく似ている。
それぞれの作家がしっかり個性を発揮してこそ、地中美術館はよりドラマチックな体験として来場者の心に刻み込まれるのだ。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

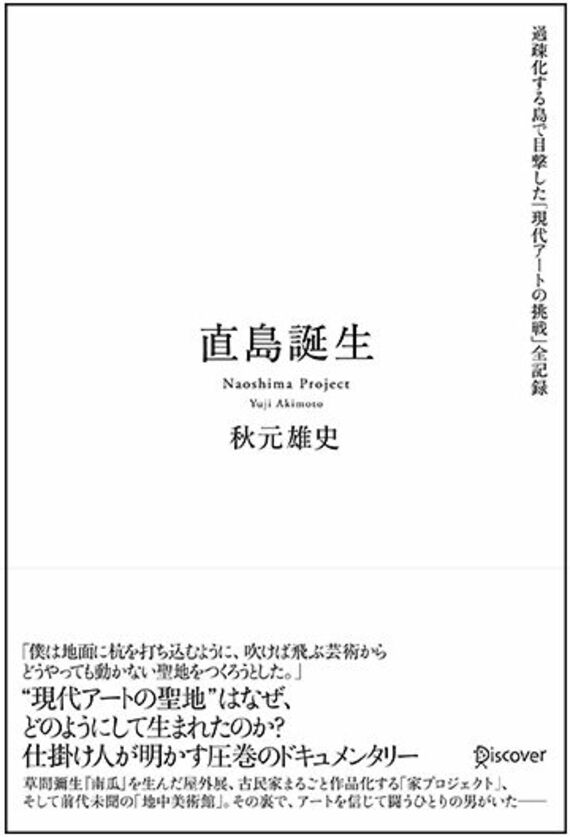






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら