自然災害対策と「財政問題」は、分けて考えろ 「赤字だから対策できない」には根拠がない
仮に長期金利が今の30倍に跳ね上がったとしても、利払い費は9兆円にも満たないのだ。その程度の利払い負担が国税収入を上回る可能性を心配することを、杞憂と言う。
第三に、それでも金利の上昇を回避したいというのであれば、中央銀行が国債を買い取ればよい。実際、日本銀行は、そうしている。いわゆる量的緩和がそれだ。
要するに、吉川氏の言う「『亡国』の財政破綻」(金利が上昇して政府の利払い負担が国税収入を上回る)のリスクは、ほとんどないのであり、しかもその極小のリスクですら、経済政策によって容易に克服できるということだ。
これに対し、「『国難』としての自然災害」の発生確率は「『亡国』の財政破綻」よりもはるかに高い。しかも金利上昇による経済損失と違って、自然災害により失われた人命は、取り返しがつかない。
そう考えると、「『国難』としての自然災害を機に、『亡国』の財政破綻に陥ってしまう」などという主張は、とうてい受け入れられるものではない。
個人や企業の借金のアナロジーで考えてはならない
それにもかかわらず、日本は財政危機であり、公共事業費を増やすことはできないという思い込みは、依然として根強い。
確かに、これまで述べたような「財政赤字を拡大すべきである」「政府の財政破綻はあり得ない」「政府債務は完済する必要がない」といった議論は、「借金は返さなければならない」という家計や企業の一般常識に反するものであり、感覚的には受け入れ難いであろう。
しかし、政府債務と民間債務とでは、制度的にまったく異なる。政府の借金を、個人や企業の借金のアナロジーで考えてはならないのだ。この政府債務を民間債務と同じように考える通俗観念こそが、あり得ない財政破綻への恐怖を掻き立て、国民の生命・財産を守るために必要な公共事業の実施を阻んでいるのである。
本来であれば、財政についての間違った通俗観念を修正し、世論を正しい方向へと導くのが、経済学者の役割であろう(参考)。
ところが、我が国では、影響力のある経済学者の多くが、逆に通俗観念に乗じて財政危機を煽り、防災対策に必要な公共事業費の拡大にすら反対してきたのである。そして、彼らの声に影響されて、政治家も一般国民も、財政健全化こそが優先されるべきだと信じ込んできた。
その結果、過去20年にわたって、公共投資は抑制され続けた。あの東日本大震災を経験したにもかかわらず、その後の公共投資はさして増やされなかった。最近の大阪北部地震や西日本の大規模水害を目の当たりにしてもなお、公共投資の拡大を求める声は小さい。むしろ財政健全化の必要性が声高に論じられている。これが、我が国の現実である。
このような状況の中で、根強い通俗観念に反し、権威ある経済学者たちの多数派の見解に抗して、財政赤字の拡大を訴えたところで、誰が耳を傾けようか。こうなっては、もはや「『国難』としての自然災害」を避けることは不可能ではないかという絶望感に襲われる。
だが、希望はまったくないというわけではない。自民党の若手議員でつくる「日本の未来を考える勉強会」は、今年の5月、防災対策(国土強靭化)の強化をはじめとする積極財政を求める提言書をまとめ、安倍首相に提出した(参考)。一縷の望みは、意外なことに、日本の政治の一部にあったのだ。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

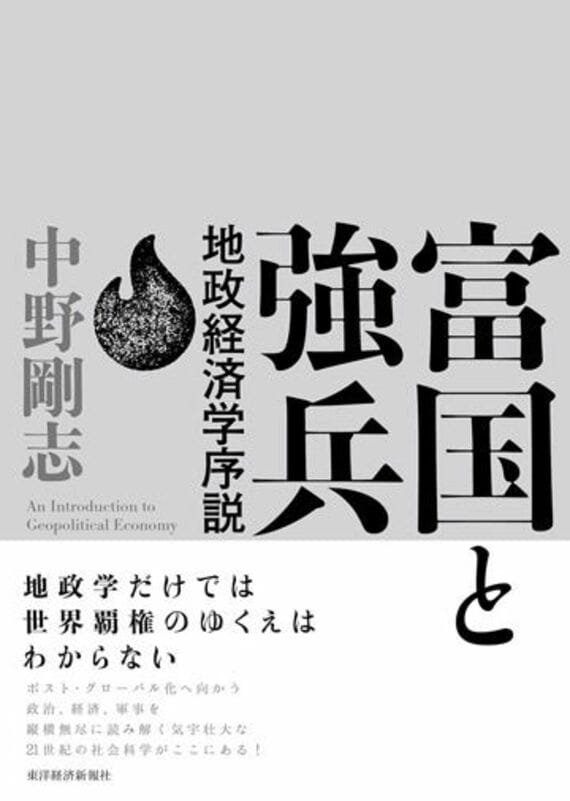






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら