【難関大合格者数3ケタ】創立241年、福岡の名門校・修猷館の強さに迫る!先生が1年間生徒になる独自の研修で磨く指導と、生徒の「語る文化」とは?
毎年2~3人の教員が実施しています。同じ教科を選ぶ教員もいますし、あえて異なる教科を選ぶ教員もいます。私の担当教科は化学ですが、渡邊先生の物理の授業を受講しました。
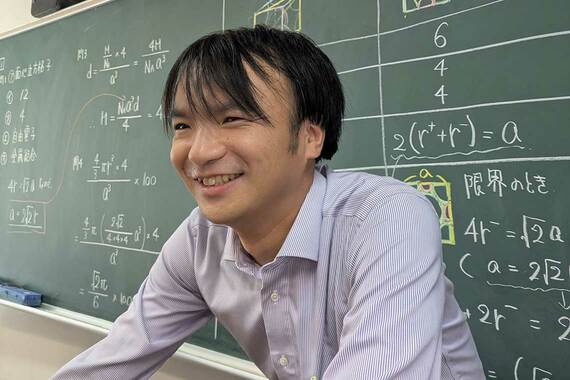
化学と物理の伝え方の違いや、共通点や結びつきも理解できて、自身の授業をするうえで非常に参考になりました。また、授業を受ける立場である生徒の受け止め方を実感できるのもとてもよかったですね。
渡邊 先生と一緒に授業を受けるのは、生徒にとってもいい刺激になったようです。若い先生だから話しかけやすかったのか、授業の後は、私よりも坂本先生に声をかける生徒が多かったですね(笑)。
松隈 また本校では3年生に対して独自の模試(修猷模試)を、5教科全科目にわたって年に3回催しています。作問をする過程で、とくに若い先生が鍛えられます。
渡邊 職員室は、各学年の教科単位で机が配置されているので、複数人の教員がいる英語・数学・国語の科目だと隣同士、あるいはくるりと椅子を回せば、教科の話ができます。教員同士で、よく教科談義をしています。雑談の中で、「宿題の量はどうしてる?」などのコミュニケーションも取っていますね。
―― 授業のほかにも、教養教育として探究活動などに取り組んでいます。
渡邊 総合的な探究の時間の「課題研究」では、1・2年生が交ざって、似たようなテーマの生徒が集まってグループをつくり、研究を行います。生徒の興味・関心にあわせて気象学や建造物、コミュニケーションなど30種類くらいの講座が開かれます。
生徒が自主的に進め、教員はサポートをします。総合的な探究の時間に調べるので時間も8時間程度と短いのですが、完成させるというよりは研究に対するきっかけになってくれればと考えています。
卒業生が芥川賞受賞、職員や生徒が推し本を紹介
―― 卒業生の鈴木結生氏が、第172回芥川賞を受賞しました。教養教育において読書の推進に注力していますが、そのたまものでしょうか。
坂本 毎朝10分間、朝読書の時間を設けており、できる限り教員も一緒に好きな本を読みます。あとは春と秋の2回、全職員が推し本を紹介しています。教員だけでなく、クラブ活動や生徒会などで活躍した生徒のお勧め本などを紹介することも。































無料会員登録はこちら
ログインはこちら