「勤労国家レジーム」とは、所得減税と公共投資によって成り立ち、社会保障などは個人と市場に委ねるというモデルだった。だが、それは低成長時代を迎えて行き詰まることになった。一人ひとりの所得の増加に頼ったモデルであったため、高度経済成長期の「所得倍増計画」のように上昇傾向にあるときにしか有効に機能しなかった。
やがて長年にわたる実質賃金の低迷によって中間層は崩壊し、多くの人々が生活苦と老後の不安に見舞われることになった。つまり、高度経済成長期から日本はそもそも「自己責任社会」だったのであり、社会保障は恥を忍んで「施される」との考えが強く、「選別性」「限定性」が生み出されたというのだ。
そのため、誰が得をしているのかという疑心暗鬼が渦巻く「再分配の罠」が広がることになる。「パイが減少し、社会のニーズが変わり、所得も減っていく状況の中では、以上の限定性、選別性は、『既得権』をもつ者への嫉妬やねたみの原因となる」と(同上)。
井手は、この「再分配の罠」について、所得階層間・地域間の不信感が高まる事態を想定していたが、先のフクヤマの議論でも触れたように「負担の分配」においてもまったく同種の罠が待ち構えているのだ。特定の階層や集団だけが恩恵を受けているというフラストレーションは、自分の階層や集団だけが割を食っているというフラストレーションに容易に転化する。
このような「負担の分配」に対する反発が蓄積すればするほど、異なる階層間の緊張は増していくことになるだろう。公共交通が充実している都市部の住民にとって、走行距離課税はどうでもいい話に思えるかもしれない。むしろ、今後利用することもない田舎の道路にお金を払わずに済むと考える向きもあるだろう。しかし、世代間の「負担の分配」に置き換えれば小さな問題ではないことがわかる。
若い世代から上の世代への富の移転
経済学者の小黒一正は、国民が生涯を通じて政府にどれだけの負担をし、受益を得られるかという視点で、世代ごとに推計を行っている。
これを「世代会計」と言い、道路・ダムなどの社会資本や、治安・国防、医療・介護などの公共サービスから得られる受益と、そのサービス供給に必要な税金、保険料といった負担などをカウントするという(『財政危機の深層 増税・年金・赤字国債を問う』NHK出版新書)。




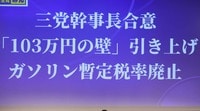


























無料会員登録はこちら
ログインはこちら