店舗数がじわじわ減少、オーケーやロピアに劣勢のなか…ほっかほっか亭が始めた「"おかずを選べる"カスタマイズ弁当」は何が凄い?狙いは?
さらに、こうした「お弁当」というカテゴリーでの直接的な競合のほか、例えば「すき家」のような牛丼チェーンも値下げを行い、高まる節約志向に先手を打って対応しようとしている(もっとも、すき家の場合、今年3月に発生したネズミ混入事件の影響を払拭したいという思いも強いのだろうが)。
このように、中食市場・外食市場を広く見渡すと、弁当屋の競合はあまりに多く、そしてどれも強敵なのである。
弁当屋の強みを打ち出した「カスタマイズ弁当」
そのような中で、弁当屋が「選ばれる」ためにはどうすればいいか。その一つの答えが「カスタマイズ弁当」だったのではないか。
スーパーにできなくて、弁当屋にできるのは、弁当屋ならではの多品目のおかずを用意し、なおかつそれを好きなように選択してもらうことだ。スーパーではどうしても効率の面から、同じ弁当を大量に作らざるを得ない(だからこそ、低価格が実現できているのだが)。外食チェーン店も同様だ。弁当屋の場合、どちらにしても注文を受けて作るのだから、それぞれのおかずさえ用意できていれば、カスタマイズがやりやすい。
カスタマイズできれば、それぞれの懐事情に合わせてメニューを変えられる。そうすれば、昨今の物価高に対応したい消費者心理にも、ある程度対応できる。
「弁当屋ならでは」の強みが活かされ、それが結果的に消費者心理にも対応できているのが、このカスタマイズ弁当だといえよう。
カスタマイズ弁当は6月に関西で発売され、人気を博している。それは、おそらく今書いてきたような理由があるだろう。
ただ、この成功が、ほっかほっか亭全体の業績を底上げするほどかどうかは定かでない。個人的には、導入店舗の少なさや、モバイルオーダー限定であることが消費者の購買の障壁になっている気もする。また、いくら値段を調整できるとはいえ、そこそこの量を食べようと思えば1000円を超してしまうのも、やはり気になるところではある。
むろん、この辺りは物流の問題や店舗の人手の問題もあるから、一朝一夕には解決できないだろう。ただ、徐々に使い勝手が改善されていけば、最終的に弁当屋の存在意義も高まるのではないか。
いずれにしても、スーパーや外食チェーンが弁当屋のポジションを脅かしていることは確かなこと。このカスタマイズ弁当がその状況にどう一石を投じるのか、見ものである。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

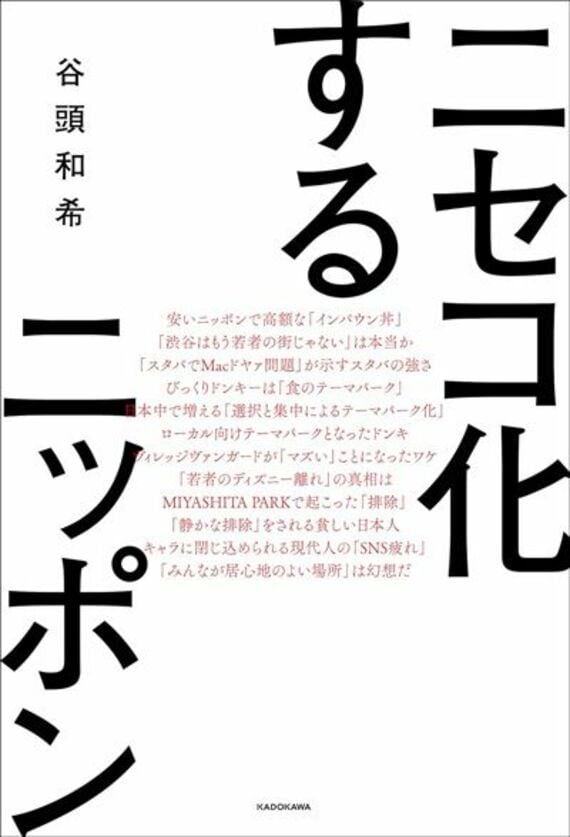
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら