ソフトバンクもついに「空飛ぶ基地局」実現へ。大手4社が挑む「空からつながる携帯」の激戦
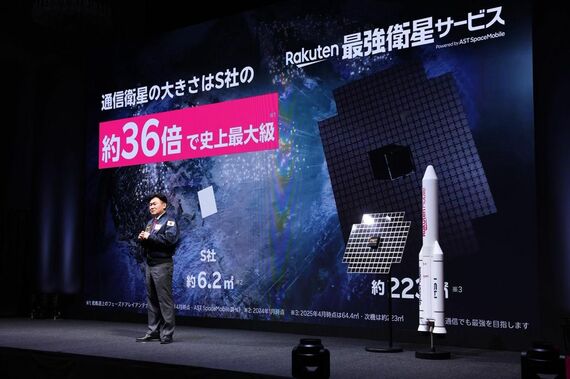
ソフトバンクは早期からHAPSを推進し続けてきたこともあり、90以上のHAPS関連特許を強みとしている。飛行機型の開発を継続しながら飛行船型で早期実用化を図る戦略は、リスク分散と技術蓄積の両立を狙う。宮川潤一社長は「10年かけて実現する」と長期的な視点で取り組んでいる。一方で低軌道衛星についても2026年度に導入予定としている。
なぜソフトバンクは飛行船型を選んだのか
HAPSの最大の利点は、衛星より地上に近いことだ。低軌道衛星でも高度300キロメートル以上を飛行するのに対し、HAPSは高度20キロメートルの成層圏に滞空する。この「近さ」が大きな違いを生む。
「衛星通信では上り速度に課題がある。スマートフォンの微弱な電波を数百キロメートル先の衛星がキャッチするのは難しい」(ソフトバンク・プロダクト技術本部ユビキタスネットワーク企画統括部の上村征幸統括部長)
一方、20キロメートルという距離なら、通常のスマートフォンでも安定した双方向通信が可能になる。音声通話やデータ通信も、地上の基地局とほぼ同等の品質で提供できるという。
興味深いのは、ソフトバンクがHAPSの早期実現のために機体タイプを追加したことだ。同社は2017年からアメリカ・AeroVironment社と共同で、翼長78メートルの巨大な無人航空機「Sunglider」を開発している。太陽光パネルで発電しながら飛行する、いわば「飛行機型」のHAPSだ。この開発は継続しながら、今回新たに飛行船型も採用した。
しかし今回採用したSceye社の機体は、ヘリウムガスで浮上する「飛行船型」だ。全長65メートルの機体は、紫外線や低温に耐える特殊素材で覆われている。なぜ飛行船型も追加したのか。

宮川社長は6月26日の株主総会で、この転換について説明している。「従来は翼を持つ飛行機タイプで開発しておりました。けれども、今回並行して検討していた新たなタイプの機体で、想定してきたよりも早くサービスを開始できることになりました」
さらに「当社のスケジュールでは2029年をターゲットに商用化を見込んでおりましたけれども、このLTA型で2026年から商用を開始できることになりました」と、3年前倒しの意義を強調した。
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら