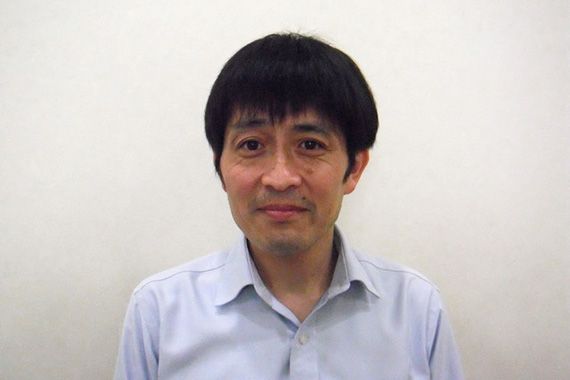
立命館宇治中学校・高等学校教諭 数学科教諭、キャリア教育部長
立命館中学校・高等学校教諭を経て、2008年度から立命館宇治中学校・高等学校でキャリア教育部の立ち上げを行う。同校が2018年度から文科省研究開発学校、2019年度から文科省WWLの指定を受けながら、探究×キャリア教育を大切にした総合的な探究の時間のカリキュラム開発を行った際に責任者としてカリキュラム開発に関わる。著書に「高等学校 新学習指導要領 数学の授業づくり」「探究の現在地とこれから」(いずれも明治図書)など
(写真:立命館宇治中学校・高等学校提供)
新しい言葉が登場すると「何のため」が抜け落ち、「なぜそれをするのか」が理解されないまま、「どうするか」というやり方ばかりが議論されてしまいがちです。そして、教科学習と探究どちらが大事なのかという二項対立が起きてしまうのです。
もしかしたら、この記事をお読みの先生の学校でも、そんな対立が起きているかもしれません。
しかし、探究が学校教育に取り入れられるようになったのには理由があります。酒井氏も、なぜ今探究なのか、HOWではなく本質を捉えて自分なりのWHYを考えることが大切だと言います。そこでまずは、その理由について確認しましょう。
今回の学習指導要領で語られているのは、生徒が社会の変化に主体的に関わり、よりよい社会と幸福な人生の創り手となるという視点です。そして、予測不能な新しい時代に求められる資質・能力は、変化の激しい社会を生きる力であり、具体的には自分で課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する能力だと書かれています。
つまり、学習指導要領で語られている生きる力とは、生徒たちの卒業後のその先まで考えた時に必要な力ということになります。
総合的な探究の時間をキャリア教育の視点で捉える
酒井氏の学校では、2018年から「総合的な探究の時間」を先行実施してきました。その特徴は、総合的な探究の時間をキャリア教育の視点を持って行うことでした。
なぜ探究の時間にキャリア教育なのか。それは、酒井氏が長くキャリア教育を行ってきたからでもありますが、「総合的な探究の時間で大切なのは課題と自分の関係。自分の将来を考えるということは、キャリア教育にほかならない。だからこそ、キャリア教育の視点を持って取り組むことが重要だ」と言います。それは、「なぜ高校で総合的な探究の時間が設けられているのか」という問いの答えにも通じる意味があります。
先が見通せない時代に、自分が自分の人生の主人公として主体的に生きるためには、社会に出る前に自分のあり方や生き方を考えられるような学びが必要です。とくに高校生は目前に迫った自分の進路選択に際して、多様なロールモデルに出会いながら自分に向き合い、その中で、学び続け成長し続ける力を育んでほしい。
そのプロセスが、まさしく探究的な学びであり、総合的な探究の時間をキャリア教育の視点を持って行う理由なのです。
では具体的にどのような取り組みをしているのでしょうか。































無料会員登録はこちら
ログインはこちら