【日本は有事に弾薬を確保できる?】ウクライナ侵攻が露わにした防衛産業の「サプライチェーン危機」。ロシアは武器の「買い戻し」も
砲弾だけではない。ウクライナ侵攻の当初、アメリカから供与された対戦車ミサイル・ジャベリン(FGM‐148)の活躍が報じられた。このミサイルの製造元であるRTX(表1‐6で2位)の最高経営責任者(CEO)は、侵攻からの10カ月で5年分の生産量が消費されたと述べている。また肩打ち式地対空ミサイル・スティンガー(FIM‐92)はジェネラル・ダイナミックス(同5位)が製造しているが、同じ期間に13年分の生産量がウクライナで使われた。
平時から「弾薬の確保」について考える
ロシアも同様の事態に直面している。ロシアが使う旧ソ連規格の弾薬の製造設備を持っている国は多くない。北朝鮮はその少ない国の1つであり、ロシアに野戦砲弾900万発を供与したと報じられている。それ以外にも、ロシアについてはイランやベラルーシから武器の提供を受ける可能性が指摘されている。
ロシアの武器製造工場は全力操業中だが、それでも消費量には追い付かない。そこでロシアは、過去に輸出した武器の「買戻し」に着手した。買戻し先としてミャンマー、インド、そして北朝鮮が疑われている。
武器だけではない。ロシアの戦車製造業であるウラルヴァゴンザヴォートは、ミャンマーに輸出した高性能の光学照準器を買い戻した。戦車の消耗が続く中、同社は旧式戦車の改良を請け負っていたと見られる。なおウラルヴァゴンザヴォートは表1‐6では10位にあるロステックの子会社で、ウクライナ侵攻以降にEUが課した経済制裁対象企業のため、西側諸国からは輸入ができない。ロステックは日本が実施する経済制裁の対象企業ともなっている。
湾岸戦争(1990〜1991年)やイラク戦争(2003年)、イラク安定化作戦(2003〜2011年)、アフガニスタン安定化作戦(2001〜2021年)では顕在化しなかった弾薬の供給が、ここに来て西側だけではなくロシアにおいても大きな問題となった。
もちろんこれは、対岸の火事ではない。日本においても安全保障三文書のいずれにも、「弾薬の確保」についての記述がある。しかしウクライナ侵攻から見えてくるのは、その難しさだ。
いざとなったら生産は間に合わず、日露戦争の時のように外国から弾薬を緊急輸入せざるを得ない。平時から同盟国や同志国などと、このための関係を構築することが望まれる。「弾薬の確保」は、単に「在庫を積み増せばよい」というものではない。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

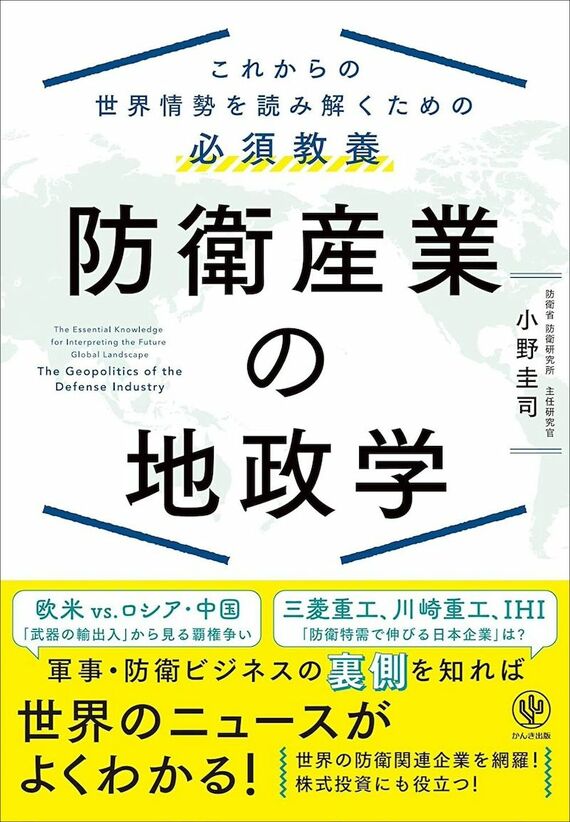






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら