円安批判を忖度した日銀の利上げは間違っている 「今は政策金利が低すぎるから」は正しい判断か
さらに、今回の展望レポートには「人手不足感が高まるもと、マクロ的な需給ギャップの改善に加え、賃金と物価の好循環が引き続き強まり中長期的な予想物価上昇率が上昇していく」などの表記がある。需給ギャップの改善が根拠にならず、利上げが正当化できないので、「人手不足感」という定性的な要因を追加利上げの根拠として重視し始めたのである。
いわゆる人手不足の状況は、企業や産業によってさまざまで、ともすれば「人材が枯渇している」という企業の声は大きくなりがちである。一部の「大きな声」に、経済全体に左右する金融政策の判断が影響されることは危ういだろう。
なお、2024年12月の完全失業率は2.4%と安定しているが、2018年後半から2019年半ばまで失業率は2%台前半で推移していた。つまり、当時よりも、現在はやや失業率は高いのだから、実際には労働市場はさらに逼迫する余地がある。失業率という重要な指標が、金融政策の判断として重視されない説明は、筆者が知る限り日本銀行から聞かれない。
円安批判を忖度した「前のめり利上げ」は大きなリスク
今回の利上げは金融市場へのサプライズとはならなかったが、根拠が曖昧で前のめりな利上げ継続によって、結局は日本銀行が目指す中立金利への利上げが難しくなるのではないか。時間をかけて慎重に判断することで、日本経済の正常化と中立金利への利上げは十分実現可能と筆者は考えているのだが、「前のめりな政策判断」はその実現を危うくするだろう。
筆者の最新著書『円安の何が悪いのか?』では、アベノミクス発動当初に黒田東彦前総裁が行った金融緩和強化がいかに効果があったかを実証、「円安悪玉論」を批判している。
緩和強化に批判的だった経済メディアや市場関係者らの多くが、2022年以降に「悪い円安」と喧伝していたが、実際には、金融緩和で大きく円安が進んだ2022年を経て、名目賃金の上昇率がようやく年3%を上回るところまで上昇している。
根拠曖昧な「円安批判」への政治的な配慮が、前のめりにしか見えない日本銀行の政策姿勢に影響しているのだろうか。日本銀行の断続的な利上げは、正常化実現が近づきつつある日本経済、株式市場にとって看過できないリスクになりかねない。
(本稿で示された内容や意見は筆者個人によるもので、所属する機関の見解を示すものではありません。本記事は「会社四季報オンライン」にも掲載しています)
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

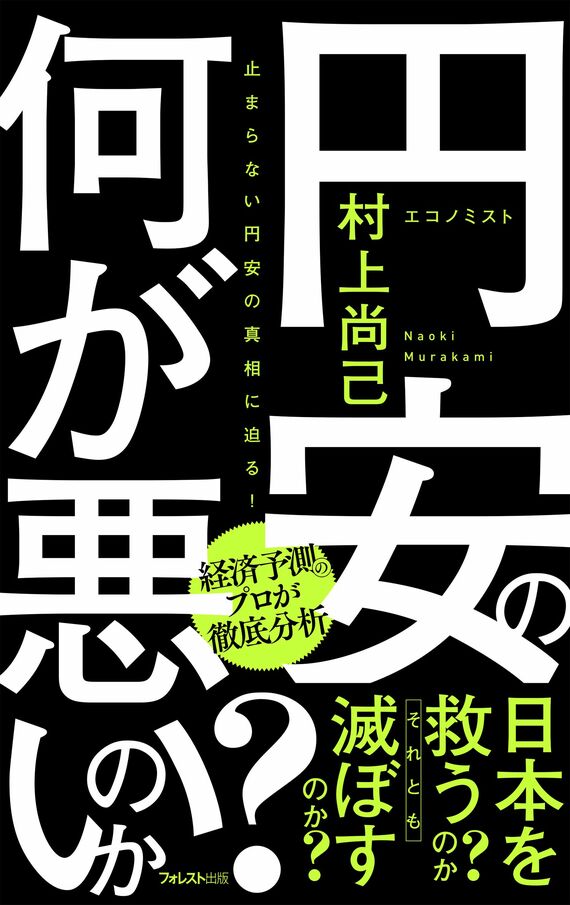































無料会員登録はこちら
ログインはこちら