生活困窮者や地方の医療を支えてきた済生会を襲う厳しい現実。

済生会は絶対に潰れない──。全国で83の病院を運営するほか、介護老人保健施設など計405施設・437事業で約6万6000人の職員を雇用する済生会は、日本最大の社会福祉法人だ。
1911年に明治天皇が生活困窮者を救済するために設立したという歴史もあり、歴代の総裁は皇族が担い、現在は秋篠宮皇嗣殿下が務めている。規模の大きさと、皇室と歩んできた歴史。それこそが医療業界で「潰れない」といわれてきたゆえんだ。
ところが昨年、関係者を震撼させる出来事が起きた。宮崎県門川町にある済生会日向病院が、銀行から融資を断られ、運転資金がショート寸前に陥ったのだ。
融資が遅れて資金不足に
門川町の人口は約1万7000人。人口の減少が続き、病院経営は厳しさを増している。それでも、新型コロナウイルス感染症関連の補助金もあり、2020〜2022年度は黒字だった。
しかし、2023年度に経常赤字に転落。昨年3月には内科を担当していた院長が急死し、同時期に別の内科医2人も退職してしまった。医療スタッフが不足したことで、新規患者の受け入れを制限せざるをえなくなった。

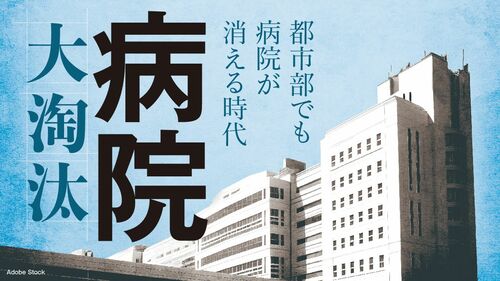

































無料会員登録はこちら
ログインはこちら