平均年齢60代と高齢化してしまった税理士業界。「若年層をつかまえよう」とハードルを下げる、今こそが受験の狙い目か。

税理士の高齢化が進んでいる。2014年の日本税理士会連合会の調査によると、税理士の半数以上が60歳以上。一方で20代は0.6%、30代は10.3%と、落差が激しい。国家資格でも税理士試験といえば難関。だが、そうした純粋な“試験組”以外に、税務署に一定年数以上勤務し実務を経験すると試験を免除されるなど、“税務署OB”が相当数を占めているのも、その一因とされる。
こうした傾向を受けて2022年の税理士法改正では、2023年4月1日以降の試験から受験資格要件が大幅に緩和されたのである。
そもそも税理士試験は、「会計学」の2科目(簿記論、財務諸表論)が必須だが、受験するには、日商簿記1級合格などの条件を満たす必要があった。これが撤廃されることで、高校生や大学1年生でも受験できるようになる。また「税法」では9科目中3科目を選択する必要があり、今までは大学で法律学か経済学を履修しなければならなかったが、社会科学の科目まで拡充され、文学部や理工学部の学生も挑戦しやすくなった。

](https://tk.ismcdn.jp/mwimgs/b/5/440/img_b517c84205e60be574cfa40faca655fe155164.jpg)
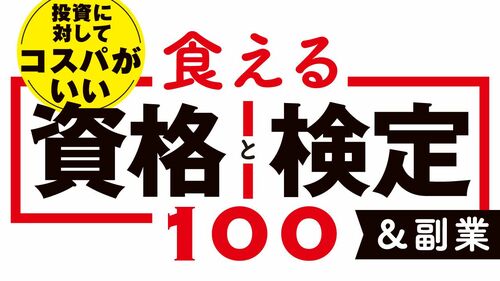

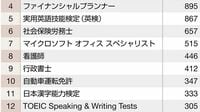





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら