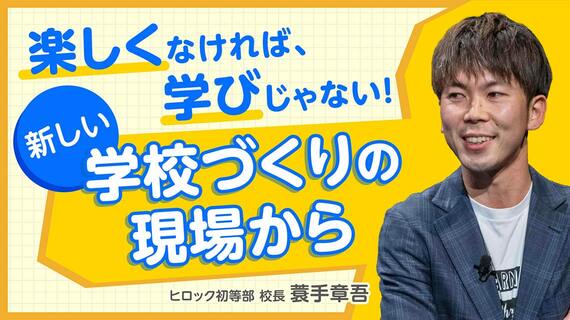学びに向かう力にとって大切なのは、コンテンツ自体が持つ魅力を子ども自身が実感できることだと思っています。その際に重要となるのが、子どもたちが自分で見つけた、自分で選んだと思えているかどうかです。心理学の世界でも、自己決定が及ぼす充実感や満足感の影響は多くの研究で実証されています。
また、この「食」という探究学習が、公立学校で言うところの「社会科」の枠に収まっていないということも重要なポイントです。公立学校ではあらかじめ教科の枠や配当時間が決められており、また内容に関しても教科書等で事前に定められています。しかし、子どもたちが本当に知りたいことや学ぶ中で自然と立ち上がってくるような問いは、必ずしも教科の枠や教科書の範囲にとどまっているとは限らないですよね。
私たち大人の社会は教科で分かれていない
今回の例で考えてみると、実際に野菜を育ててみることは教科で言うなら理科的だし、金額の計算や時間経過を振り返ることは算数的な学びです。そんな子どもの興味関心に対して「今は社会の時間だから」とか「それは来年の学年でやるから」と言って取り下げるのは、極めて大人の都合と言えそうです。
そもそも、私たち大人の社会は教科で分かれていませんよね。興味や課題が目の前に現れたとき、いちいち「これはなんの教科だろう」なんて考えないはずです。もちろん、公立学校でも今日「教科横断的な学び」や「カリキュラム・マネジメント」といって、教科の枠を超えて授業全体を設計していこうという方向にはなっていますが、制度の面などまだまだ多くの難しさや障壁があるのが実態と言えそうです。
今回は「テーマ(コンセプト)から始まる探究学習」を例に、「自分で自由に選べる」という要素と「枠にとらわれない」という2点についてご説明しました。次回は「興味関心(コンピテンシー)から始まる探究学習」を例にご紹介できればと思います。
(注記のない写真:蓑手氏提供)
執筆:蓑手章吾
東洋経済education × ICT編集部
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら