
僕が「プロジェクト学習」を始めた訳
僕は教員になって今年で21年目ですが、これまで毎年テーマを決めて「個人研究」に取り組んできました。
初任から4年間は主に奈良県の土作彰先生による「ミニネタ」という小さな学習コンテンツを学んで引き出しを増やし、5年目から7年目は東北福祉大学の上條晴夫教授のアイデアを参考にお笑いの要素(フリ・オチ・フォローなど)を学校生活の中に取り入れるほか、コスプレでほかの先生になりきる「パフォーマンス授業」なども開発しました。
8年目以降は、プロジェクトアドベンチャー(※1)や体験学習法、「作家の時間」(※2)や「読書家の時間」(※3)といったワークショップ授業に出合い、研究実践をスタート。同時期に日本協同教育学会にて協同学習も学び始めました。
※1 アドベンチャーを用いた体験教育を提供する米国発祥の組織
※2 「ライティング・ワークショップ」という米国発祥の実践
※3 「リーディング・ワークショップ」という米国発祥の実践
中でも「作家の時間」との出合いは僕を大きく変えました(関連記事「驚くほど作文が好きになる『書く力』の伸ばし方」)。かつて作文指導に力を入れた時期があったのですが、子どもたちの文章力をある程度伸ばすことができたものの、「書くことが好き」という子はなかなか増えませんでした。そんな中、「自ら書こうとする『書き手』の育成」を目指す「作家の時間」を実践したところ、子どもたちがどんどん自分から書くようになっていったのです。「これからの時代に必要なのは、こういう『自ら学び続けようとする力』なのだ」と実感しました。
フリーランスティーチャーになって4年目に、東京都日野市の公立小学校で勤務できたことも現在の教育観に大きな影響を与えています。日野市では、ちょうど僕が勤務した年から、「一律一斉の学びから自分に合った多様な学びと学び方へ」「自分たちで考え語り合いながら生み出す学び合いと活動へ」「わくわくが広がっていく環境のデザインへ」といった次世代型の教育方針に大きく転換したのです。その教育目標に共感し、子どもが自ら学びのコントローラーを持つことに重きを置く実践に取り組んできました。
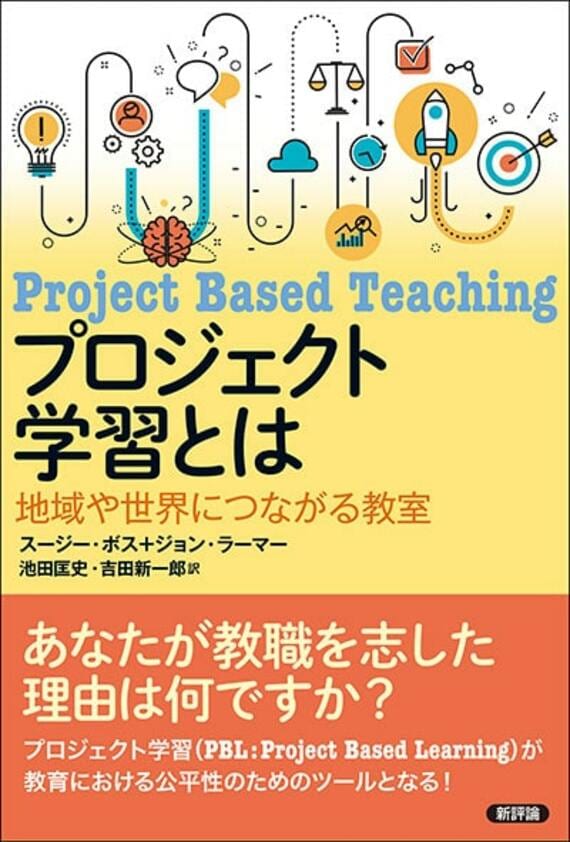
そんな中で「探究」という言葉をよく見聞きするようになり、情報収集する中で出合ったのが、『プロジェクト学習とは 地域や世界につながる教室』という本です。米国でプロジェクト学習(Project Based Learning/以下、PBL)が盛んに取り組まれるようになった背景やその必要性、効果や具体的実践例が記されています。僕は今、この本を参考にPBLに取り組んでいます。
PBLとは、一言で言うと「学習を、より児童・生徒中心にするための仕組み」です。質の高い学習体験を促進することを通して、児童・生徒が自ら学び続ける「学び手」に育っていくことを目指します。それまで学び実践してきた「作家の時間」「プロジェクトアドベンチャー」「協同学習」と目指すゴールは同じだと感じました。






























