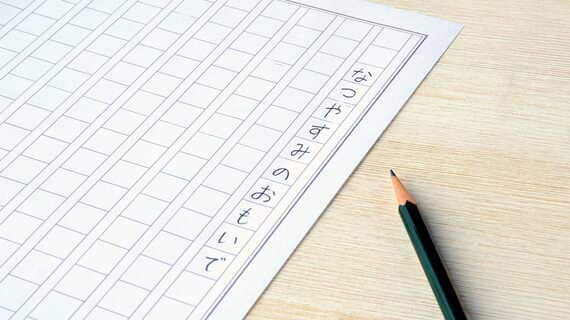
――作文を夏休みの宿題に設定した学校も多いと思いますが、書くことに対して苦手意識を持つ子どもは少なくありません。田中先生は、どのような作文指導を行っていますか。
僕は14年間、「作家の時間」という実践を続けています。これは米国発の「ライティング・ワークショップ」という実践で、日本でも同名タイトルの著書が新評論から出版されています。
この本を翻訳した吉田新一郎先生や軽井沢風越学園校長の岩瀬直樹先生らが国内で実践を広めてきましたが、僕は14年前、その実践者グループの1人である甲斐崎博史先生と同僚でした。当時、甲斐崎先生の教室をのぞくと、子どもたちが喜々として書くことに取り組んでいました。それを見て感動し、僕も取り入れるようになったのです。

(イラスト:田中氏提供)
プロの作家と同じプロセスを体験させる
――「作家の時間」と一般的な作文指導は、どう違うのでしょうか。
「作家の時間」が目指すのは、「自ら書こうとする『書き手』の育成」です。従来の作文教育は「よりよい文章を正しく書くこと」など技法的な点が重視されがちですが、「作家の時間」では子どもたちの表現する内容に重きを置いています。ここが大きな特長であり、僕が最も感銘を受けた点でもあります。
僕はかつて、「楽しんで書く」を大切にしながら作文指導を行っていました。あえてウソを盛り込んで書く「うそ日記」、物語をアレンジする「パロディー作文」、1文ずつ交代しながら書く「鉛筆対談」といったさまざまな実践に取り組みましたが、作文についてのアンケートを取ると「苦手」「嫌い」という声が思いのほか多かったんですよね。
「授業中の食いつきはいいのになぜだろう」と悩んでいましたが、「作家の時間」と出合ってよくわかりました。僕のそれまでの実践は、単発の取り組みとしては効果的なのですが、継続的なモチベーションが生まれにくい。一方、「作家の時間」は体系的に作られていて教員も子どもも理解しやすいため、「もっと書きたい」という気持ちにつながりやすいのだと思います。そこも大きな魅力です。
――どのような学習体系なのでしょうか。
まずは執筆ジャンルの選定。「新聞製作」「報告文」といった学習指導要領にあるジャンルはもちろん、小説や物語などさまざまな執筆ジャンルの中から子どもたちが自分で書きたいジャンルを決めます。そのうえで、プロの作家がやっているプロセスを体験させる実践になっています。
































