
「文化をつくる」ため、「当たり前の見直し」をベースに
僕は2021年9月から、PBLの実践に取り組んでいます。
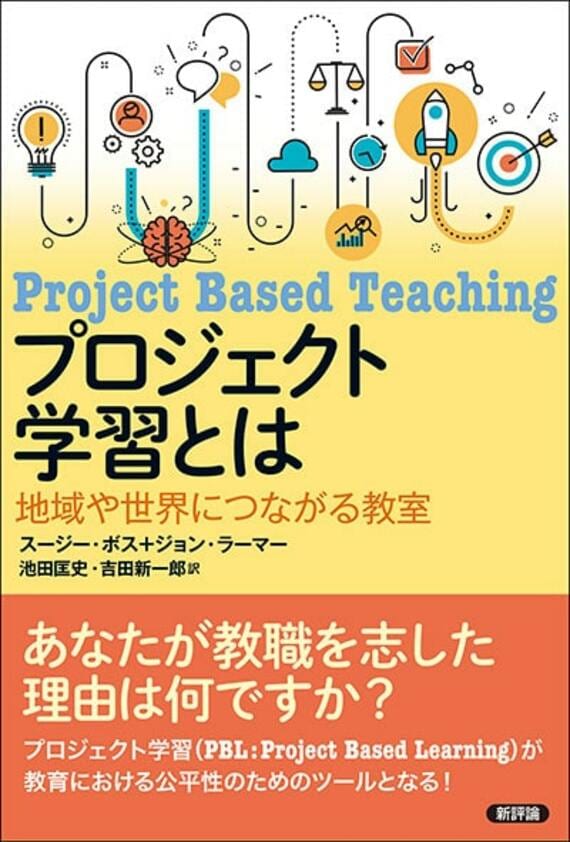
参考にしているのが、『プロジェクト学習とは 地域や世界につながる教室』という本。同書に示されている「ゴールドスタンダード」というプロジェクト設計に不可欠な7つの要素と7つの「教師の役割」を指針とし、特別活動(学級活動)の中でPBLを行っています。
具体的には、「クラスプロジェクト」と題し、クラスの仲間のためにやってみたいことの実現に取り組んでいます。前編では小学2年生の学級におけるPBLの導入の様子に触れましたが、今回はその後どのようにゴールドスタンダードを活用してクラスプロジェクトを進めていったのかをご紹介したいと思います。
ゴールドスタンダードと教師の役割は以下のとおりです。まずはゴールドスタンダードの「挑戦的な問題や疑問」については、学校の中の「当たり前」に着目しました。
1:挑戦的な問題や疑問
2:継続的な探究
3:「本物」を扱う
4:生徒の声と選択
5:振り返り
6:批評と修正・改訂
7:成果物を公にする
【ゴールドスタンダードにおける7つの教師の役割】
1:文化をつくる
2:学習をデザインし、計画する
3:スタンダードに合わせる
4:活動をうまく管理する
5:生徒の学びを支援する
6:生徒の学びを評価する
7:生徒は夢中で取り組み、教師はコーチングする
引用:『プロジェクト学習とは 地域や世界につながる教室』
例えば、「席に着いて授業を受けましょう」「宿題を忘れずにやりましょう」といったものや、最近広がっている「〇〇学校スタンダード」なんかもそうですね。よかれと思って大人の都合を押し付けてきた結果、子どもは「指示どおりにこなす力」が身に付くものの、「自分で考え判断し行動しなくてもよい」という意識が刷り込まれてしまいました。
だから僕は、PBLを通して学校の「当たり前」を一つひとつ子どもたちと見直しています。これにより、本当の意味で「文化をつくる」ことができるのではないかと考えています。
ここをベースに「継続的な探究」として取り組むことにしたのが、「クラスプロジェクト」です。子どもたちからは多くのアイデアが出て複数のプロジェクトが誕生しました。
例えばその1つであるお化け屋敷プロジェクトでは当初、数名の子が「お化け屋敷をやってみたい!」と言い出し、わいわいと相談が始まったのですが、「学校側が許してくれるかな?」なんて声が出てきました。































