社会起業家の育成で見えた「課題解決人材」3特徴 ボーダレス・ジャパン共同創業者「失敗が重要」

なぜ「ソーシャルビジネス」しかやらないのか?
2007年創業の「ボーダレス・ジャパン」は、「ソーシャルビジネスしかやらない」という異色の会社だ。「ソーシャルビジネスで世界を変える」をミッションとし、現在世界16カ国で42の事業を展開している。
例えば、同社グループには、妊娠・授乳期の女性をターゲットにしたハーブ商品を販売する会社があるが、これはミャンマーの農家の貧困解消を目的に立ち上がった事業だ。そのほか、過疎化、差別・偏見、地球温暖化など、解決に挑む課題は多岐にわたる。

社会課題の解決を強く願う者たちが集い、互いに資金やノウハウ、人的資源などを共有しながら各自がソーシャルビジネスに取り組むという独自の「社会起業家プラットフォーム」を構築し、20年度の売上高は約55億円、従業員約1400名を抱える一大グループ企業に成長した。
今でこそ日本のソーシャルビジネスの代表格として注目される同社だが、創業当時はSDGs(持続可能な開発目標)のような社会課題に対する共通認識もなかった時代で、慈善的な「ソーシャル」と収益化を目指す「ビジネス」を結び付けるには多くの困難が伴ったはずだ。にもかかわらず、なぜソーシャルビジネスに特化した事業を展開し始めたのか。同社副社長の鈴木雅剛氏は、こう振り返る。
「社長の田口一成は大学生の時、自分の人生で何をすべきか模索する中、テレビで見たアフリカの子どもたちの映像に衝撃を受け、世界の貧困問題をなくすために動き始めました。一方、僕は塾講師のアルバイトをしながら、仕事にやりがいを感じられない人、あるいは働きたくても働けない人がたくさんいることを知り、『誰もが働く時間は幸せであるべき。そのために社会や仕組みを変えていきたい』と考えていた。そんな2人が大学時代に出会って意気投合したことが、当社の始まりです」
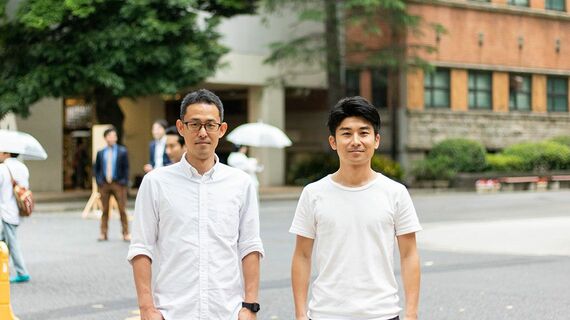
ただ、当初は社会課題をビジネスで解決するという発想はなかったという。考えたのは売り上げの1%を寄付すること。それが社会の標準になれば世の中は変わると思い、賃貸仲介業で起業して寄付を始めた。しかし、相手の顔は見えず、何が変わったのかもわからない。しだいにモチベーションの維持が困難になっていった。
「そこで、ビジネスの内容と社会課題を解決したいという目標を直結させることにしたのです。外国人が部屋探しに苦労している現実や日本人と交流する機会がない問題に着目し、日本人と外国人が共に暮らせる多国籍シェアハウス事業を始めました」

これを機にソーシャルビジネスに特化するようになり、右肩上がりの成長を続けてきた。1つひとつの事業が大きくなるだけでなく、事業の数も増えている。






























