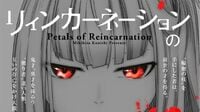社会起業家の育成で見えた「課題解決人材」3特徴 ボーダレス・ジャパン共同創業者「失敗が重要」
「社会課題とは個々人の課題の集合体であり、解決の選択肢やアプローチも多種多様です。だから、世界の問題を解決するには事業の数をたくさん生み出すことが大事」と鈴木氏は話す。こうした考えの下、同社は独自のシステムで社会起業家を増やしてきた。社会課題に対する思いの強い人を採用し、いきなり社会起業家として独立採算の企業を経営させるのだ。
各起業家は、グループから最大1500万円の資金が手渡され、採用・投資・報酬のすべてを自己決定して経営を行う。資金が尽きれば事業は終了するが、再チャレンジも可能だ。目安として、プロダクトができると、1年以内の月次黒字化と、トータル約3年での累損解消を目指す。通年で黒字を達成した起業家は余剰利益を拠出。そして、各社から集められたその資金を別の新たなソーシャルビジネスの投資に回す。同社はそんな独自の「恩送り」の仕組みで成り立っている。
一般的なピラミッド型の企業組織とは異なり、あくまで主役は社会起業家たち。彼らが事業に集中できるよう、マーケティングや資金調達、経理、法務、労務などについて助言するバックアップスタジオという専門部隊も設けて支えている。
これからの時代に「求められる人材」、3つの特徴
いわば同社は、1人ひとりが何をやりたいのかを明確に持った社会起業家の集合体。しかし、どうやって人材を集めているのか。
採用基準は、シンプルだ。「自分はこの問題を解決する」という強い思い、それに対する行動や考え抜いてきたプロセスを評価する。「新卒採用は、マインドセットや行動力を重視。プランを持ち込んでもらうキャリア採用は、強い思いとビジネススキルの両方を求めています」と、鈴木氏は説明する。
しかし昨今、社会課題に関心を持つ若者は増えているものの、同社の新卒採用は起業を前提としていることがハードルとなっているようで、応募者は少ないそうだ。キャリア採用も、マインドとスキルを兼ね備えた人が少ないため、応募者は多いものの参画できるのは年に数人程度という。日本にはまだ、課題解決型の人材が足りていないことがうかがえる。
だが、社会課題は山積している。そんな時代に必要な人材について、鈴木氏は具体的な特徴を3つ挙げる。それは、「失敗できる人」「目的を持って探究できる人」「『対他者』『対社会』の視点で目的を追求できる人」だ。とくに「失敗」は重要なキーワードだという。
「実は今、失敗できる人がほとんどいません。学校教育のモデルが明治期以降、変わっていないからです。与えられた仕事を時間内に正確にやれる人材の育成に主眼が置かれてきたので、まずやってみて失敗したら改善していくという試行錯誤型の思考ができないのです」
最初からネットや書物で「正解探し」をしてしまい、実際に誰が困っているのか、誰が喜んでいるのかもわからない。子どもも大人もそのようなマインドだから、既存の枠を超えられない。「新たなものを見いだしていくには、失敗を恐れずトライできる力が必要です」と、鈴木氏は強調する。
昨今、やりたいことがわからないという若者が少なくないが、鈴木氏も「志をどう持てばいいのか」「自分が取り組むべきことをどう決めたらいいのか」とよく聞かれるそうだ。そんなときは「まずは気になることについて深めなさい」と答えるという。
「調べたり話を聞きに行ったりする探究プロセスの中でいろんなことが見えてくる。最初からやりたいことが明確な人なんてほとんどいません。頭でっかちにならず、まずは行動してみることが大事」と、鈴木氏は言う。また、せっかくやりたいことがあっても内にとどめてしまう人が多いので、人に話してみることも大切だという。
「大抵9割は無反応ですが、1割は共感してくれたり誰かを紹介してくれたりします。そういった応援や助け合いの中でまた新たなものが見えてきて、いつの間にか本当にやりたいことにたどり着く。そんなふうに自分の目が外に向くことが重要です」