日本企業はデジタル時代の「巨人」たちとどう対峙すればいいのか。経営共創基盤の冨山和彦会長に聞いた。

――かつて隆盛を誇った日本の携帯電話や液晶テレビ業界は、構造変化に対応できませんでした。
デジタルテクノロジーとネットワークの発達でネットフリックスなどが現れ、映像コンテンツがネット空間で直接提供されるようになった。顧客は「サービスそれ自体」に価値を置くようになり、テレビのようなハードウェアはコモディティー化して価値が低下。ハードウェア単体の日本の製造業は苦戦を強いられている。
携帯電話においても、アップルのiPhone、グーグルのアンドロイドOSという破壊的イノベーションにより、産業アーキテクチャーが大転換。通信キャリアを頂点とするヒエラルキー構造が崩壊し、日本の携帯電話産業は存在感を失ってしまった。
バーチャルとリアルの組み合わせ
――日本企業の勝ち筋はどこにあるのでしょうか。





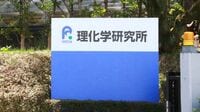



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら