“刺さる表現”の方向を誤ると、企業のブランドを毀損することも。しかも高速で拡散する。
SNSで誰もが情報を発信できる時代。著名人や企業、団体の言動にネット上で非難が集中する、いわゆる「炎上」案件は、年々破壊力を増している。
デジタルリスクコンサルが主力のエルテス社によれば、2020年には国内で1000件近い炎上が発生。いろいろなパターンがあるが、炎上まではおよそ、次のような過程をたどる。

番組や広告、ポスターで自分が不快に感じたものを目にすると、まず、①一部のユーザーが批判をSNSに投稿、②それに共感したほかのユーザーが拡散する。さらに、③影響力ある著名なインフルエンサーやネットニュースが取り上げ、最悪の場合、④マスメディアが報道したり、デモ活動に発展したり、行政指導にまで至ったりするのが、典型的なパターンだ。
ここ数年は、企業の広告やSNSでの投稿にジェンダーに関する偏見があるとして、炎上するケースが後を絶たない。

女性=運転苦手の先入観
トヨタ自動車の場合、19年にツイッターの公式アカウント上で行ったアンケートで、女性ドライバーに「やっぱり、クルマの運転って、苦手ですか?」と質問。答えにあった選択肢は、「とても苦手」「すこし苦手」「どちらでもない」「得意です!」の4つだった。「やっぱり」と、女性は運転が苦手だとの先入観に基づいた表現に加えて、回答の4択中2つが「苦手」だったことで批判を浴びることに。トヨタは当該ツイートを削除することになった。

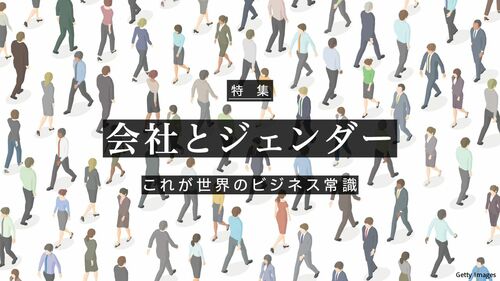



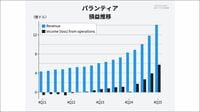



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら