
・国家は路傍の花を踏みつぶしても前進しなければならない ヘーゲル
・優れた人間は個人的道徳を超越することが許される ヒトラー
「歴史ブーム」といわれてすでに久しい。
確かにここ十余年、わが国の出版界は大量の「歴史もの」を出してきた。しかもその内容は、世界や日本の通史から超長編の大河小説、英雄・奇人の伝説、さらには推理小説顔負けの古代謎解きものや人を驚かす奇説の類で、至りて尽くさざるなしの観がある。
新しきを知るための歴史
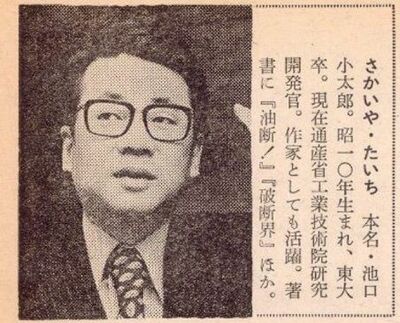
こうした中に、私がさらに一文を加えるのは、全くの蛇足かもしれない。それにもかかわらず、あえて筆をとったのは、ここで書こうとしているものが、従来の「歴史もの」とはいささか違った観点と主題とを持つだろう、と考えたからである。つまり、歴史を単なる「昔物語」としてではなく、現代の問題、とりわけわれわれ一般の庶民にもかかわりの深い身近な問題として、現実と将来を予測するよすがとして見直してみたい、ということである。































無料会員登録はこちら
ログインはこちら