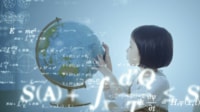その後、幸いなことに14歳で高校を卒業、5つの大学に奨学金付きで合格という幸運に恵まれるのですが、このことを可能にしたのは僕の中にあった「やればできる」という「根拠のない自信」のようなものだったと思います。この「根拠のない自信」は、いわゆる「セルフエスティーム」=「自尊感情」「自己肯定感」と呼ばれるものが大きく関係していたと思います。僕はカナダで、この「セルフエスティーム」がとても大事だということを、知らず知らずのうちに身に付けていたんだと思います。
カナダの教育では、対象はどんなことでもよい。結果ではなく「行動」や「過程」、チャレンジしたこと自体を褒める、そしてそれを繰り返します。失敗したら、「チャレンジした行動」を褒め、成功したら「その努力の過程」を褒める。こうしたことを、それこそ幼稚園の頃から高校卒業に至るまでずっと毎日繰り返すわけです。こうした繰り返しで「セルフエスティーム」を持ち、高めていくことが目標をかなえていくために必要な力、すなわち困難を克服し、物事を成し遂げるために必要な力になると僕は思いますね。
日本のギフテッド教育は身近なところに
――ご自身で受けてこられたカナダのギフテッド教育と、日本のギフテッド教育との比較、そこから見えてくる課題や評価できる点についてはいかがでしょうか?
日本の教育に関しては、経験が少ないので詳しいことはわかりませんが、一般的にカナダの教育で感じたことは、
(1)結果がどうであれ、積極的に取り組んだことに対して、強く称賛される
(2)スピーチやプレゼンテーションなど多くの人の前での発表機会が頻繁にある
(3)先生が教えるというより、グループ学習を通じて仲間内で学んでいくパターンがとても多い
(4)クリエーティブな事柄への評価が高い(物語を創作したり、絵本を作ったりなどの課題が多い)
ことなどが挙げられます。これらの点は、通常教育だけではなく、カナダのギフテッド教育においてもまったく同じでした。ギフテッド教育の場合、これらに加えて、
(5)チャレンジする!
という点に重点が置かれていた気がします。
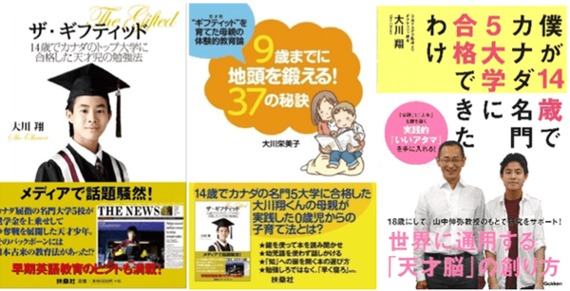
日本のギフテッド教育は制度化されていないのかもしれませんが、表立ってギフテッド教育と銘打つことはなくとも、実際のところ、それは行われていたのではないか、と僕は思っています。事実、僕が所属している孫正義育英財団には、合計で240人の財団生がいますが、まさに異能集団で、皆さん実に目を見張るような活動をしています。彼らは全員ギフテッドと言えるのではないでしょうか。
では日本の場合、どういったところでギフテッド教育が行われているのか。例えば、学習塾や予備校で行っている授業の中には、学校の授業内容の枠を超えた、ギフテッド教育と言ってもいい内容のものが含まれている気がします。日本の中学受験用に勉強した特殊算と呼ばれる算数は、実は、カナダで受けたギフテッドプログラムの算数の授業やコンテスト数学の問題にかなり類似しています。また、自由度の高い私立学校の授業内容や、教職に限らず、優秀な教育者の方が個別に担っていた教育の中にも、ギフテッド教育に該当するものがあるんじゃないかと思います。こういったものが、いわゆる「吹きこぼれ」の子どもたちに対応してきたのではないか、と感じます。
最近取り上げられているギフテッド教育は、2E (Twice Exceptional)※に対しても、民間の学習機関が対応し始めたというところだと思います。日本でも学校教育のような大きな船は舵を切るのに時間がかかりますが、小さな船なら小回りが利きます。学習塾、予備校、NPO団体などは、現状のギフテッド教育の問題点に合わせて、素早く対応できるのではないかと期待しています。
※特定分野で異能があるギフテッドの中には、2E(Twice Exceptional)と呼ばれる、ギフテッドであり、自閉症スペクトラムやADHD、LDなどの発達障害をあわせ持つ人たちもいるといわれています
――日本の学校の先生や保護者がギフテッドの子どもに対してできる支援や、必要な視点とは?
極端な例かもしれませんが、知的障害を持ちながら、3歳のころにはすでに、卓越した絵画の才能を発揮していた少女が、自閉症の学校に入学し、そこで言葉の教育を重点的に受けた結果、彼女の言語能力は改善した。しかし、幼い頃に見せていた天才的な絵画の才能は失われたという話があります。どうするのが正しいのか、とても難しい問題です。
ギフテッド教育は、子どもたちの高い潜在能力を生かし、それをさらに伸ばすための特別なプログラムという意味合いが強いと思います。しかし、学校教育には、単に知的学習をするだけではなく、社会への適応を学ぶ場という側面もあります。「出る杭は打たれる」ということわざがあるように、学校などで集団生活を送っていると、時に突出した能力は、和を乱す行動と取られ、攻撃の対象になったりすることがありえます。異分子を排除しようとする防衛的な行動は、もともとは仲間を守ろうとする働きだと思いますが、それは、時には、いじめに発展するケースもある。この場合、いじめている側は、悪いことをしている自覚がない場合もあるでしょう。
ギフテッドは人と違う行動を取ったり、そのパフォーマンスゆえに、仲間になじめず、攻撃の対象となりやすかったりするかもしれません。その攻撃をはね返す力を持っている人はよいですが、人によっては不適応を起こし、その結果不登校になるなどのギフテッドもいるのではないかと思います。教育現場にいる大人たちにそういったことへの理解があるとよいと思います。要は、能力を伸ばしつつ、不適応を起こさないようにするというところでしょうか。ギフテッド教育も含め、そのさじ加減がカギになるだろうと僕は思います。