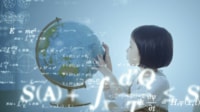よく質問されるのですが、いわゆるビデオゲームやオンラインゲームの類いは、興味がなかったわけではありませんが、当時はほとんどやっていません。意識してそうしたというより、物理的に時間がなかったという感じです。また、意外かもしれませんが、両親から「勉強しろ」と言われたことはありません。子どもの頃、生活面で両親から最もよく言われたことは、「早く寝ろ」です。「いつまでも勉強してないで早く寝ろ」とはよく言われました。振り返ってみると、幼い頃、カナダという新しい環境に放り込まれ、強い危機感を持つことができ、さまざまな体験をし、いろいろチャレンジできたことが現在の自分につながっているような気がします。
――ほかにも大量の本を読んだり、公文式、七田式などさまざまなものに触れたりしてこられたようですね。
そうですね。大量の本を読むきっかけとなったのは、英語ができなかった危機感からです。さらに、幼い頃から親にたくさんの本の読み聞かせをしてもらったことは、本を読む習慣がつき、多読に役立ったと思います。公文式や七田式の思い出は、たくさんプリントをやって、積み上げたら自分の身長くらいになっていて、「なんかたくさんやったなあ」というある種の達成感があったことです。公文式や七田式というのは、目に見えない形で血肉になっていて、これらは基礎体力をつける訓練だったと思っています。
高校生になった頃から、積極的に行動するようになり、自分の興味につながる活動を開始するようになったのですが、幼い頃に基礎体力を鍛えてきたおかげで、その後の活動がスムーズに進んだように思います。それは勉強の習慣であったり、計画の立て方、失敗したときの分析、対処の仕方、わからないことを調べたりするスキルなどです。
勉強面だけで判断されないギフテッド
――ご家族やご本人がギフテッドと気づかれたきっかけは何だったのでしょうか?
グレード3(小学校3年生)の時、小学校の担任の先生から「翔はギフテッドかもしれない」と言われたのがきっかけです。自分では自覚はありませんでしたし、親から何か言われたこともありません。
なぜ担任の先生がそう判断したのかはわかりませんが、そのことを言われる少し前に、クラスで自主的にイベントをやったことがありました。友達4人を誘ってグループをつくり、僕が短い物語を創作し、セリフを書き、絵を描き、小道具を作ったりして、クラスみんなの前で発表しました。ちょっとした劇のような感じで、クラスでとても評判がよかったんです。その後に、担任の先生から言われたので、もしかしたら、いわゆる勉強面だけじゃなくて、そういう創造力というか、何か物事を新しくクリエートしていくところを見て、担任の先生が、ギフテッドかもしれないと判断したのかなという気はします。
先生からは「ギフテッドプログラムという、いろいろ面白いことにチャレンジできるプログラムがある。今のクラスにいながら、ギフテッドプログラムの取り出し授業が受けられるよ。認定試験を受けてみたらどう?」という話を聞き、それならいいなと思い、認定試験を受けることになったのです。
その後、学校認定の試験、教育委員会認定の試験や、心理学の先生との面談などを経て、「ギフテッド」の認定を受けました。待ち時間も多かったので、最終的に認定されるまで1年くらいかかったような気がします。僕の通っていた小学校は600人くらいの生徒がいたのですが、ギフテッドに認定されていたのは、学校全体で5人でした。しかし、「ギフテッド」は1つの尺度にすぎません。「ギフテッド」というのは、同世代の子どもと比べて何らかの分野で高い能力を持つ子どもを指す相対的な概念であって、「ギフテッド」だからすごいと思われがちですが、日々の努力を怠るようなら、認定は無用の長物、百害あって一利なしだと思います。
――ギフテッドプログラムは、どのようなものだったのでしょうか。
ギフテッドプログラムには、学校単位のものと、教育委員会単位のものの2種類がありました。どちらも、普段のクラスとは違う、何らかの新しいチャレンジができる場所、という感じでした。例えば小学校時代でいうと、シェークスピアを原文で読み、イギリス発音をまねて練習。実際に劇を他の学校の生徒たちの前で演じたり、みんなでプロのシェークスピア劇を見に行ったりしました。ほかにも、数学コンテストの準備のための講義を受けてみんなで解き方を発表し合ったり、うそ発見器を作ったり、現役の作家や大学教授の話を聞きに行く、なんていうのもありましたね。クイズ大会や、物語を書いて発表し合うということもあり、結構楽しかったです。高校時代は、みんなで議論したり、ライティングをしたりしていました。
日本の中学受験対策が飛び級につながった
――大川さんが歩んできた道は、前例のないことも多かったと思いますが、そうした中で、自分の目標をかなえていくために必要な力とは何だったのでしょうか。
そもそも僕は、友達と一緒にいたくて、担任の先生から言われた飛び級の話を当初断っていたくらいで、最初から人と違う道を進みたいと思っていたわけではありません。いずれは日本で中学受験をして、その後は日本の学校に通うつもりでいました。そのため、並行して日本の中学受験の勉強もしていたわけですが、結果的にこの受験勉強自体が、飛び級につながることになります。後で知ったのですが、飛び級は英語力で決まるそうです。実は、帰国子女枠の英語入試はかなり難易度が高く、カナダの先生たちに、帰国子女向けの渋谷教育学園幕張中学校の入試問題を見せたら、多くの先生がグレード10~11(高校1年~2年生)レベルと回答したほどです。中学受験も、中途半端な気持ちで受かるような試験ではなかったので、必死に勉強していました。その勉強が、結果的に学年の飛び級にもつながったわけです。11歳で飛び級の認定試験を受けたときには、英語力がグレード10(高校1年生)でもトップクラスと判断されました。
2012年1月、中学受験で渋谷教育学園幕張中学校(帰国子女枠)を受験し、合格。その時点でカナダでは、ほぼ全科目グレード10(高校1年生)へ進級していました。そのとき、究極の選択を迫られたのです。日本に戻り中学1年生として進学するか、それとも、カナダでグレード11(高校2年生)に進級するのか。カナダで飛び級の道を先に進めるのは、まさに道なき道を行く感じです。誰もロールモデルがいません。飛び級を進めたからといって、大学に早く行ける保証もないのです。そのため両親と、メリット・デメリットについて、かなり話し合った記憶がありますが、最終的にはカナダで飛び級を続けることを選択しました。失敗してもいいから挑戦してみようという気持ちが強かったのだと思います。