ITの天才、小・中・高校生から育成する「未踏ジュニア」の凄み 日本は才能を「発掘し育てる」プログラムがない

17歳以下の小・中・高校生が対象、最大50万円の資金援助も
経済産業省所管の独立行政法人情報処理推進機構(IPA)では、IT分野において突出した能力を持つ人材を発掘、育成するため、2000年度から未踏事業を行っている。
「未踏は25歳未満を対象にしています。年齢に下限はありませんが、どうしても大学生以上が多くなりがちです。大学生や大学院生には大学の研究室があり、自分のアイデアを膨らませたり、考え方や方法を教わる機会があります。しかし、そういう機会が小・中・高校生にはなかなかなく、もっと環境が整えば伸びる子はたくさんいると考え、未踏ジュニアを始めました」
こう話すのは、自身も未踏事業の卒業生であり、現在は未踏ジュニアの代表を務める鵜飼佑氏だ。未踏ジュニアは、独創的アイデアと卓越した技術を持つクリエーターを育成するプログラムを16年から行っている。
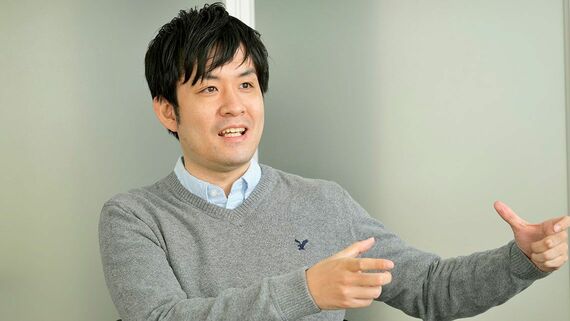
未踏ジュニア 代表
東京大学大学院にて水中ロボットを用いた水泳支援システムの研究開発を行い、2011年度IPA未踏事業スーパークリエータに認定される。16年に、一般社団法人未踏にて未踏ジュニアを代表として立ち上げ、現在まで業務外で運営を行う。本業では、MicrosoftのOfficeやMinecraft開発チームにて教育関連の製品のProgram Managerを務めた後、King's College LondonのComputing in Education専攻に留学。文部科学省にてプログラミング教育プロジェクトオフィサーとして主に小学校におけるプログラミング教育を推進した後、外資系IT企業にてアジア太平洋地域のコンピューターサイエンス教育をリードしている
(撮影:梅谷秀司)
プログラムの参加者は年に1度、17歳以下という条件で(下限はなし)、国籍や性別を問わずに公募している。個人に限らず、最大4人までという条件付きだがグループでの応募も可能だ。応募者は、開発してみたいソフトウェアやハードウェアを設定し、その開発計画を提出。それを未踏ジュニアのメンターが見て、書類選考と面接を行ったうえで採択するという流れだ。

































