
東大人工知能開発団体「HAIT Lab」とは?
多くの企業が生き残りを図っていく中で、最重要課題の1つとして取り組んでいるのがDXによる事業の再構築だ。これを一口で言えば、事業の生産性を高めるために、これまでの事業の仕組みなどに対して最新のITテクノロジーによって抜本的な改革を行い、デジタル時代にふさわしい企業の姿に生まれ変わらせるものということになる。教育の世界でもICT化が進んでいるが、企業では生き残りをかけて、より切迫感をもって既存ビジネスのデジタル化に取り組んでいるといえるだろう。
こうして今、活況を呈しているDXの領域で新たなビジネスチャンスを見いだし、AIによって企業のDX推進戦略をサポートするビジネスを行っているのが、STANDARDの共同創業者である安田光希(こうき)さんだ。同社は2017年に安田さんが仲間と創業したスタートアップ企業で、「ヒト起点のデジタル変革」というビジョンの下、企業の課題解決のために、DX人材育成や戦略コンサルティング、AI実装支援などを行っている。創業5年ですでに600社以上のDX推進をサポートしてきた実績を持つ成長企業だ。このSTANDARDはどのように誕生したのだろうか。
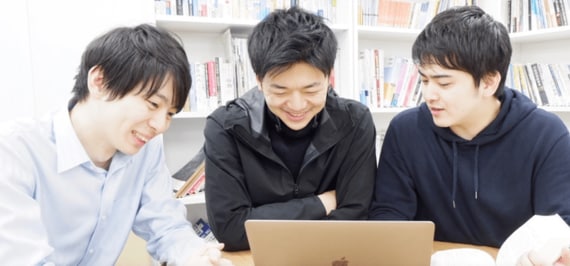
「きっかけは、東大、慶応、早稲田、九大や九工大などの学生を集めたAIについて学ぶサークル『東大人工知能開発団体 HAIT Lab(ハイト・ラボ)』です。これは16年3月に、共同創業者の石井が立ち上げ、私は同年5月から参加し、徐々にほかのメンバーも合流して作り上げていった組織です。当時はAIブームが日本でも起こり始めた頃で、文系、理系問わず、AIを勉強したいと思う学生たちが集まって、学び合っていました」
集まった学生は約100人。当時はAIに関する日本語の文献はまだ少なく、自分たちでAIを学ぶために、翻訳した文献を使用するなどしてオリジナルの教材作りを始めた。そこで学んだ学生たちが、IT企業などでインターンとして働き始めると、AIのエンジニアが足りないこともあり、18~19歳の大学生がすぐさま即戦力として扱われるようになった。それが企業の間で評判となり、あるとき、取引先の企業から「会社をつくらないの?」と後押しされたことが、STANDARDの誕生につながる。ほかのスタートアップ企業のようにベンチャーキャピタルから資金を調達することはなく、すべて自分たちの資金で立ち上げた。安田さんも得意の投資で資金を用意したそうだ。






























