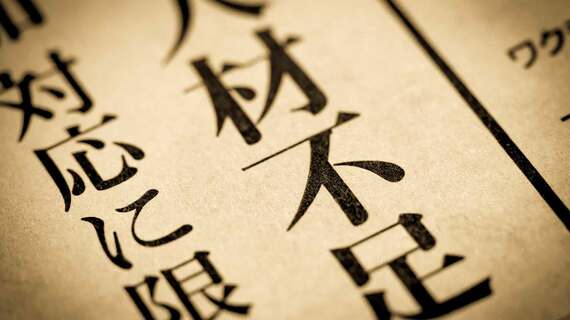
教員不足のいちばんの被害者は子どもたち
・受験生に対し、免許外の教師が授業を行うということが起こった。(愛知県中学校)
・3人に社会の臨時免許を持たせ、社会科未経験の先生が各学年に教えている。受験生の保護者からクレームがある。非常に混乱している状態。(鹿児島県中学校)
・育休代替講師が見つからず、自習で対応せざるを得なかった。(山形県中学校)
・病休補充の講師が見つからず、2クラス合同での授業を実施しなければならない状況になった。(岩手県中学校)
教員不足、講師不足に歯止めがかからない。冒頭で紹介したのは、「#教員不足をなくそう緊急アクション」※が全国公立学校教頭会の協力を得て今年4月に実施した調査で、小中学校の副校長・教頭からの声の一部だ。
※日本大学・教授の末冨芳氏、教職員の声を政策に届けるSchool Voice Project、妹尾昌俊氏による有志のチーム
教員不足とは、欠員状態を指すが、各地の学校で慢性的な人手不足となっている。労働力人口が減る中、あちこちの業界でも人手不足かもしれないが、教員不足のいちばんの被害者は、これからの社会を担う子どもたちであり、看過できない。

教育研究家、一般社団法人ライフ&ワーク代表
徳島県出身。野村総合研究所を経て、2016年に独立。全国各地の教育現場を訪れて講演、研修、コンサルティングなどを手がけている。学校業務改善アドバイザー(文部科学省委嘱のほか、埼玉県、横浜市、高知県等)、中央教育審議会「学校における働き方改革特別部会」委員、スポーツ庁、文化庁において、部活動のあり方に関するガイドラインをつくる有識者会議の委員も務めた。Yahoo!ニュースオーサー。主な著書に『校長先生、教頭先生、そのお悩み解決できます!』『先生を、死なせない。』(ともに教育開発研究所)、『教師崩壊』『教師と学校の失敗学』(ともにPHP)、『学校をおもしろくする思考法』『変わる学校、変わらない学校』(ともに学事出版)など多数。5人の子育て中
(写真は本人提供)
直近では実際、どのくらい欠員となっているのか。実は文部科学省も、誰も全国的な正確な数字を把握できていない。文科省は2021年度の4月、5月の状況を調査したきりで、あとは各教育委員会に「昨年度より悪化しましたか」などという、ゆるい調査しかしていない。こんなことでは実態をつかめないし、必要な予算を取っていくうえでも、政治家や財務省などに説得的に示せないと思うのだが。































無料会員登録はこちら
ログインはこちら