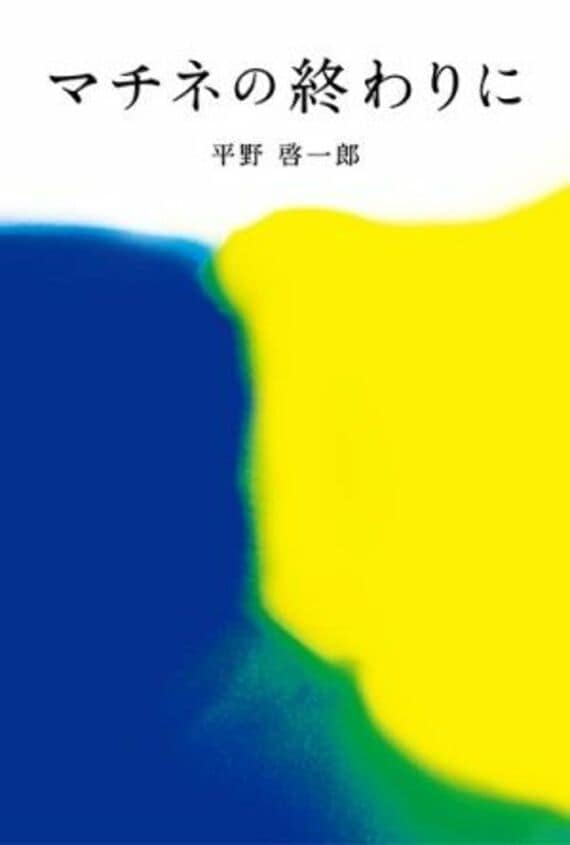閉塞感漂う社会の中、募る将来への不安

1975年生まれ。京都大学法学部卒。1999年在学中に文芸誌「新潮」に投稿した『日蝕』により第120回芥川賞を受賞。以降、一作ごとに変化する多彩なスタイルで数々の作品を発表。2019年に映画化された『マチネの終わりに』は累計58万部超のベストセラー。2020年7月末まで新聞連載していた長編小説『本心』は2021年に単行本発売予定。現在、『三島由紀夫論(仮題)』を執筆中。
「日本という国自体が、自分探しの旅を始めたような時期だった」。平野啓一郎氏は学生時代をこう振り返る。
「私が大学生だった1990年代後半は、阪神・淡路大震災やオウム真理教のテロなど『世も末』みたいな出来事が立て続けに起こっていました。バブル経済が崩壊して就職難になっていましたし、インターネットもまだ普及していなかったので、閉塞感はすごくありました。冷戦も終わり、世界情勢も変わった。『何のために生きるのか。どうやって生きていけばいいのか』ということを、かなり深刻に考えていました」
しかし、「どう生きるか」という根源的な問いへの対処法は知らなかった。
「高校までは、そういう問いを突きつけられ、真剣に考える、という授業はありませんでした。倫理の授業もありましたけど、面白いなと思う程度で、自分の問題とはなかなか接続しませんでした」
高校から大学に進学するまではそれでよくても、大学生活が後半に突入すれば、将来をいや応なしに考えざるをえなくなる。大学3年生となった平野青年も例外ではなく、焦りは深まった。そんなときに、「人生の方向が変わる」経験となる講義と出合う。それが、小野紀明氏(現・京都大学名誉教授)の「西洋政治思想史」だった。
「大学3年になると、専門科目を履修しないといけません。でも、何となく選んだ法学部なので法律には全然興味を持てず、目についたのが小野紀明先生の『西洋政治思想史』でした。文学は好きだったので思想史に魅力を感じましたし、当時大ブームだった現代思想ももう少し理解できるのでは、と期待しました」
そんな軽い気持ちで履修を決めた平野氏。初回の講義は、頬づえをつきながら教室のいちばん後ろの席で受けていた。ところが、講義が終わる頃には「一種のショック状態で、その場から動けなくなっていた」という。