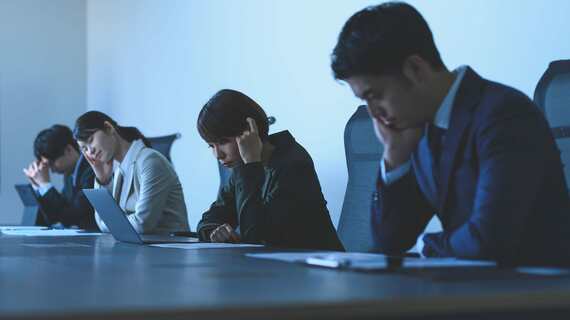
毎年8月になると、多くの日本人がアジア・太平洋戦争のことを思い出す。とりわけ、今年は大人気のNHK朝ドラ「虎に翼」でも描かれているので、あの戦争は何だったのかと、改めて考えた方も多いのではないだろうか。
そこで今回は、太平洋戦争を扱った1冊の書籍から教育行政や学校教育の実情を考えたい。戸部良一ほか(1991)『失敗の本質:日本軍の組織論的研究』(中央公論新社)だ。とても有名なロングセラー本で、政治家や経営者にはこの本を「座右の1冊」とする人も多くいる。初版は1984年で、40年前のものだが、こんにちにもとても参考になる。

教育研究家、一般社団法人ライフ&ワーク代表
徳島県出身。野村総合研究所を経て、2016年に独立。全国各地の教育現場を訪れて講演、研修、コンサルティングなどを手がけている。学校業務改善アドバイザー(文部科学省委嘱のほか、埼玉県、横浜市、高知県等)、中央教育審議会「学校における働き方改革特別部会」委員、スポーツ庁、文化庁において、部活動のあり方に関するガイドラインをつくる有識者会議の委員も務めた。Yahoo!ニュースオーサー。主な著書に『校長先生、教頭先生、そのお悩み解決できます!』『先生を、死なせない。』(ともに教育開発研究所)、『教師崩壊』『教師と学校の失敗学』(ともにPHP)、『学校をおもしろくする思考法』『変わる学校、変わらない学校』(ともに学事出版)など多数。5人の子育て中
(写真は本人提供)
われわれは何を目指しているのか…あいまいな戦略目的
『失敗の本質』で、日本軍の失敗の要因として最初に指摘されているのは「あいまいな戦略目的」についてだ。戦略ないし作戦の明確な目的がなければ、軍隊という大規模組織をバラバラに行動させることになりかねず、それは致命的な欠陥になる。
読者の皆さんにとっては、「何をそんな当たり前のことを」と思われるかもしれないが、この問題を日本軍はあちこちで起こしている。太平洋戦争のターニング・ポイントとなったミッドウェーの戦いでもだ。
(中略)一方ニミッツ(引用者注:チェスター・ニミッツ米太平洋艦隊司令長官)は、場合によってはミッドウェーの一時的占領を日本軍に許すようなことがあっても、米機動部隊(空母)の保全のほうがより重要であると考えていた。そして、「空母以外のものに攻撃を繰り返すな」と繰り返し注意していたのである。
出所:『失敗の本質』pp.100-101































無料会員登録はこちら
ログインはこちら