教員の「副業」、許可の判断基準は?現役高校教員の挑戦で見えてきた曖昧なOK /NGライン 訴訟経験と多様な申請から探るルールのあり方
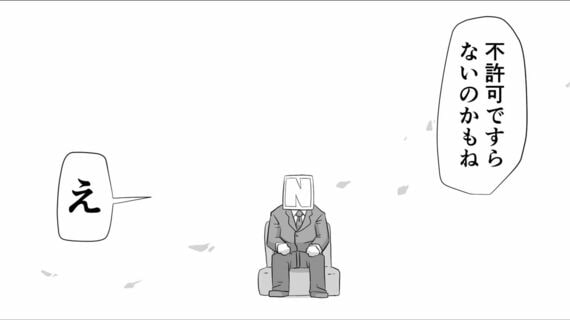
理由不明の「兼業NG」、訴訟を起こしても釈然とせず…
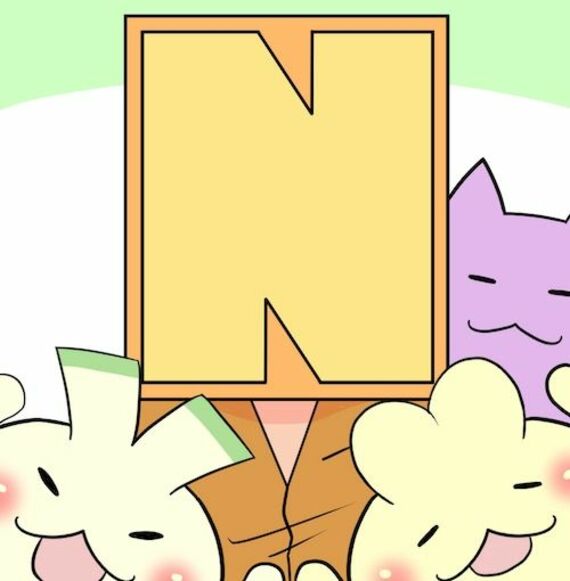
東京都立高校社会科教員/特定非営利活動法人越境先生 理事
大学の教育学部に進学し、教員免許を取得。その後大学院に進学し、専修免許状を取得。2023年3月に『パパが育休とってみたら妻子への愛が深まった話』(KADOKAWA)刊行。出版に際して行った兼業申請が理由不明のまま不許可となり、悩んだ末に訴訟を提起。その経緯や結果は自身のブログにもまとめている
X(旧Twitter)やInstagramに子育て漫画を投稿している“パパ頭”氏。わが子とのほのぼのとしたやりとりや子育てのリアルを描いた内容で人気を博している。
そんなパパ頭氏の職業は、都立高校の公民科教員だ。教員歴は今年で14年目。幼い頃から表現することや人に伝えるのが好きで、絵を描くのも好き。大学では教育学部を選び、漫画研究部に入部。教員として働き始めてからも、X(当時はTwitter)などに作品を投稿していたという。
結婚して子どもが生まれ、子育て漫画を投稿すると、それが編集者の目に留まり、書籍化の打診を受けた。ここで初めてパパ頭氏は兼業申請をすることになった。
「兼業申請の順序としては、所属する学校の経営企画室に申請書類をもらい、記載して校長に確認してもらいます。その上で、判断材料となる書類などと共に、校長が申請書を各地区のセンターに提出するという流れです」
ここで言う「センター」とは東京都学校経営支援センターのこと。都立高校とその附属中学、特別支援学校等の経営支援を行う機関だ。東京都内を東部地区・中部地区・西部地区に分け、各地区で支援センターと支援センター支所が担当地域の学校を管轄している。
パパ頭氏は経営企画室でもらった申請書に記入し、出版社が用意した出版に関する詳しい資料を添えて、校長を通じてセンターに提出した。しかし1カ月後に返ってきたのは、パパ頭氏が提出した申請書と、口頭での「許可はできない」という返答だった。


申請に対して本来受け取るはずの通知もなく、不許可の理由もわからない。悩んだ末、パパ頭氏は東京都教育委員会に対して「教育公務員の兼業のあり方を問う訴訟」を提起した。
































