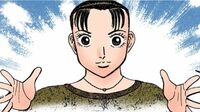では、子どもたちが“自ら考える力”、または“やる気”を向上させるにはどうすればいいのか。
それには目的や目標を映像化し、ディテールまで鮮明にイメージさせることが重要なのだという。そのためには、現状の自分の姿、課題を、他人に説明できるほど細かく理解することが欠かせない。そして、目的や目標に対して、自分がどれだけ近づいたのか、いないのか。毎日振り返りながら、目的や目標と自分の現在地との距離を把握しながら、自らを見直すことが大切だと武田さんは言う。
「私はシンクロを始めてすぐに夢中になり、大好きなシンクロについて毎日考え、自分の課題や対策、個人ランキング、ライバルのデータもすべて頭に入れていました。今のように、インターネットがある時代ではなかったので、情報を得るべくそこかしこにアンテナを立てて(笑)。小学6年の頃には、オリンピックに出場するには何をすればいいのか、そのゴールへ向かう行程表を思い描いていたほどです。そこには、こんな自分になりたい、なるんだ、という明確で具体的なイメージがあり、純粋にシンクロが好き、うまくなりたいという強い思いがあった。自分で将来を勝手に想像してワクワクしていたのです。今考えれば、それが強みだったのでしょう」
先生は、私の可能性を、私よりも信じてくれた
武田さんをシンクロの世界で一流の選手に育て上げたのは、厳しい指導で知られる井村雅代コーチだ。実際、どのような指導を受けていたのだろうか。
「非常に厳しかったですね。指導に関しては、できるようになるまで立ち会うという、すさまじい執念がありました。それはもう、言葉では表現できないような強いものです。でも、なぜそんなに激しく、厳しい指導についていけたのか。それは“あなたはできるから来なさい”という先生の思いが、根底に強く流れていたからです。先生は私の可能性を、私よりも信じてくれた。“あなたは自分で思っているよりももっとうまくできる”。だから待っていてあげるから来なさい。そう信じてくれました。それを言葉で伝えるのではなく、本能で感じさせてくれたことが大きかったと思います」
ときには言われたことが受け止められず、自分はやめたほうがいいのかと思い悩んだこともある。そんなときは、その理由を徹底的に分析し、自らに問いただした。何が嫌なのか、なぜやめたいのか、そして、それから自分は逃げるのか、乗り越えるのか。そう考えたときに、本当に嫌なのはシンクロではなく、先生に認めてもらえていないと感じている自分なのではないか。そう気づいた。認めさせずに逃げては自分の負け。そんなふうに切り替えた。

「そのとき、私は自分が傷つきたくなくて、先生に対して精神的なバリアを張っていました。でも徹底的に自分を分析し、先生に認めてもらいたいという本当の思いを知ったことで、もがいている姿でもいいから、とにかく何かを変えたいと思う自分を先生に見せなければと考えました。そうしなければ、先生から変わることはない、と考えたからです。張っていたバリアを剥がすには時間がかかりましたが、その状態から抜けたとき、先生に対して “はい”と返事をする声質が変わり、壁を乗り越えたと感じたことを今でも覚えています」