あの無印良品が味わった「停滞」の意外な歴史 成功体験に縛られれば危機が訪れるという教訓
つまり問題は「在庫そのもの」ではなく、「在庫を生み出し続ける仕組み」にありました。そしてその根本は、「セゾンの社風」──つまり「データ」ではなく「感性」や「コンセプト」を重視する体質にあったのです。
そこで良品計画が出した答えは、「MUJIGRAM」というマニュアルを作成し、あらゆる業務を明文化することでした。「MUJIGRAM」にはレジ対応から在庫管理まで、良品計画で必要となる業務について、現時点でベストプラクティス(最適)と考えられる要素が盛り込まれ、頻繁に更新されるように設計しました。それを社員に徹底させ、社風を変えることで、経験主義的な風潮を一掃したのです。
この「MUJIGRAM」こそ、良品計画にとっての、「セゾンの社風」との決別の象徴といえるでしょう。そして、水面下では発注システムを改良することで、良品計画は在庫リスクを低減させたのです。
良品計画が2006年2月期決算で、営業収益1408億円、同純利益率6.6%というV字回復を成し遂げた背景には、「MUJIGRAM」による「セゾンの社風」との決別があったのです。
「過去のベストプラクティス」に「未来の答え」はない
企業経営やビジネスにおいて「絶対的な正解」は存在しません。顧客のニーズが絶えず変化する以上、一時的に成功した手法であっても、数年後、数十年後には通用しなくなるというのが、世の中の常です。
セゾングループが提唱した「感性の経営」は、バブル絶頂期における「ベストプラクティス(最適)」でしたが、バブル崩壊後にはセゾングループを苦境に陥れる原因になりました。良品計画が「感性の経営」の間違いに気づいてセゾンという時代錯誤の社風を是正し、危機を突破したように、「どのような組織文化を引き継ぐか」を時代によって変化させなければ、生き残ることはできないのです。
ところが、世の中に目を向けると、「絶対的な正解」を求めるニーズは後を絶ちません。例えば社内に問題が起これば、多くの経営者はコンサルタントに「正解」を求めようとし、書店には「ベストプラクティス」に染まった書籍が並んでいます。世の中が変化する以上「正解は変化する」ことが本質であるのにもかかわらず、「決まった正解」を追い求めてしまうのは人間の本性なのです。
ビジネスパーソンがつねに考えなくてはいけないことは、世の中で流行している「正解」や「ベストプラクティス」を盲信することではなく、どのような時代背景においては、どのような手段が「より適切なのか」を考え抜くことです。そして念頭に置かなければならないことは「今の正解」ではなく「世の中がどのように変化するのか」ということなのではないでしょうか。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

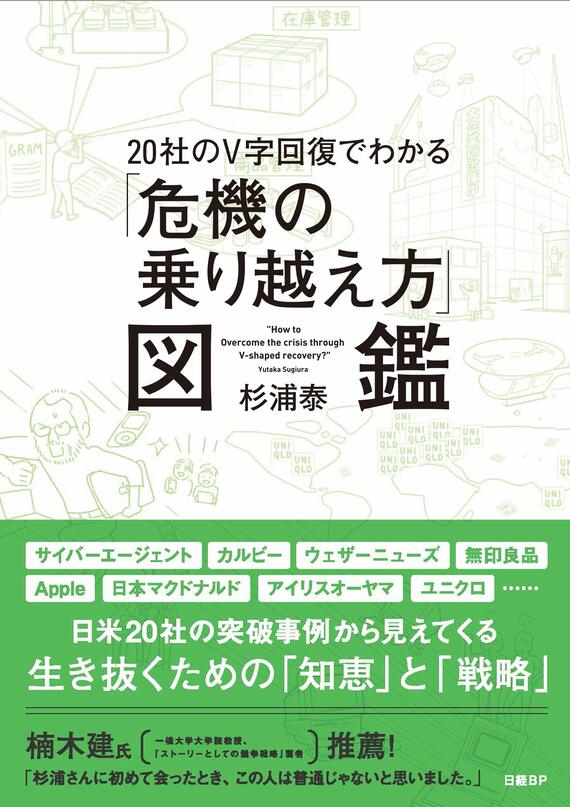






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら