歴史が苦手な人は学ぶ面白さの本質を知らない 時間軸とエビデンスで考えられるようになる
尾原:登場人物が2人しかいない場面で、まるでその場にいたかのようにセリフを書くのは、作家の「創作」ですよね(笑)。
出口:歴史は科学だし、エビデンスを積み上げて何が起こったかという真実に近づいていこうとする学問なので、物理学も歴史も同じだという気がしています。
尾原:世の中の現象はいろんなことの組み合わせで起こっているけど、その中で、いちばん影響しやすい法則を取り出せば、ある程度、未来を予測できるというのが物理学です。例えば、ロケットを飛ばして宇宙に行くには、100とか200の膨大な現象を成り立たせる法則のうち、とりあえずこの5つを再現できれば、人間は月に行けるに違いない。その5つの大きな法則を導き出すのが物理学で、それは歴史も同じですよね。
出口:そうです。ありとあらゆる学問には、そういう共通の土俵があると思いますし、エビデンスベースで人間は考えていくしかないなと。
結局は生き残ったものがえらい
尾原:ここまでのお話をまとめると、ビジネスだろうが生命だろうが、結局は生き残ったものが偉い。つまり、運やタイミングに左右されてしまうのはどうしようもないけれど、過去の歴史を学んでおけば、ある程度、運やタイミングが求められる現象を法則化することができる。それを知ることで、次の波はどこに起きやすいか、考えられるようになるし、それが見えたときにどう動けば運を手繰り寄せられるかも、わかりやすくなる。
出口:ヒントは得られますよね。歴史というのは、いろんな人々が興っては滅んでいく物語で、王朝なら王朝が、企業なら企業が興っては滅んでいく。おもしろいのは、滅んでいく場合と、新しく興る場合の法則のようなものがあって、滅んでいく場合は、簡単にいえば、世の中の流れに取り残されるグループが滅んでいくのです。
尾原:そうですね。
出口:では、滅んでいったところは改革をしなかったのかとか、世の中の動きを知らなかったのかといえば、そんなことはありません。丁寧に見ていくと、世の中の動きをきちんと理解して改革はしているのです。ただ、そのスピードが遅い。何もしなかったから滅んでいくんじゃなくて、一所懸命アヒルの水かきをするんだけれど、世界のスピードに取り残されて滅んでいく場合がほとんどです。
尾原:それ以前の環境に適応しすぎて、環境が激変したときについていけず絶滅してしまった恐竜みたいなものですよね。あと、サイバーエージェントの藤田晋さんが「スケールデメリット」という言葉を使っていますが、図体が大きくなると、どうしても速度が遅くなる。だからこそ、彼は技術に疎くても時にCTOになりゲームを牽引し、いまはAbemaというTVのオンラインへの進化にコミットする。世界の進化速度はどんどん速くなる中、経営者こそが世界のスピードに取り残されないようコミットし続けているわけですね。
(構成:田中 幸宏、第2回に続く、近日公開予定)
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

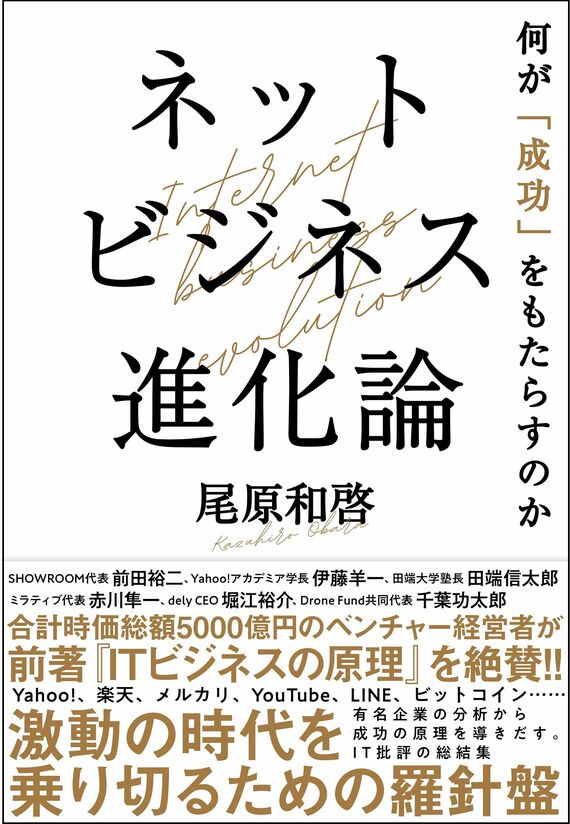






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら