漫画!東大生が「文章を速く正確に読める」ワケ 「ドラゴン桜2」に学ぶ、読解力を高めるコツ
最初と最後に、本当にキーワードが多いの? と疑問に思う人もいるかもしれませんが、実はこれこそ、東大生が速読のためによくやっている文章読解テクニックなのです。
東大生もやっている「速読」実践テクニック
東大生の中には、英語も国語も、文章はすべて「最初を読んだら、すぐに最後を読む」という読み方をしている人が一定数存在します。最初の2段落ぐらいを読んだ後に、続きを読むことなく、1度最後の段落に飛んで、文章を読んでみるのです。
「え!? そんな読み方したって、何言ってるのかわからなくなるだけじゃないの?」と思う人もいるかもしれませんが、そんなことはありません。
これは、「文章の基本の型」と深い関係があります。
・その後でその説を補強するように論を展開していく(本論)
・最後にもう1度、自分が言いたいことを話す(結論)
大抵の文章はこのように、「序論→本論→結論」という順番で話が進んでいきます。
最初と最後に言いたいことを言う……プレゼンテーションの世界では「サンドイッチフォーマット」とも言われるそうですが、これはどの文章にも当てはまる一般的な文章構造です。
ネットの記事でもビジネス書でも、新書でもセンター試験の問題でもプレゼンでも、日本語の文章だけでなく英語の文章でも、なんでも当てはまる、まったく同じ基本法則なのです。
だからこそ実は、文章の最初を読んだ後に、読み進めることなく1度最後の段落を読んでしまうことで、筆者が何を言いたいのかが理解できるようになるのです。これさえわかっていれば、「だいたいこういうことが言いたいんだろうな」という心の準備をして読み進められるので、格段に文章が読みやすくなるのです。
おすすめなのは、漫画でも出てきたとおり、最初と最後を読んで「同じような言葉は使われていないか?」と考えてみることです。その言葉は必ず、文章全体における重要なキーワードになっているはずです。
センター試験や東大の入試問題で使われているような、構造のしっかりした文章というのは、とくにこのパターンに当てはまります。過去20年間のうち12年分が、このやり方でキーワードを発見することができる文章です。それ以外の年の文章も、最初から少し読み進めた段落や最終段落の1個手前の段落を読めばキーワードを発見できるものばかりでした。
入試問題以外にも、多くの本や文章にもこの法則は当てはまります。文章の最初と最後で同じような言葉が登場していて、そしてその共通する言葉が文章全体を象徴するものになっている……ということは、本当によくある話なのです。
これを先に発見しておくかおかないかで、読解に大きな差が出てきます。
例えば、キーワードをあらかじめ理解して、全体の趣旨さえ理解しておけば、文章の中でわからない言葉や1文が出てきても「だいたいこういうことが言いたいはずだ」と、文章の趣旨から逆算して理解することもできます。
また、「きっと作者はこういうことが言いたいんだろう」とわかっているので、多少スピーディーに文章を読んでも内容が頭に入りやすくなります。誤読も防げますし、速読も可能になるのです。
いかがでしょうか? このテクニックを使って読む訓練をすれば、読むスピードはグッと早くなると思います。何度か練習して、試してみてもらえればと思います!
(漫画:三田紀房/コルク)
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

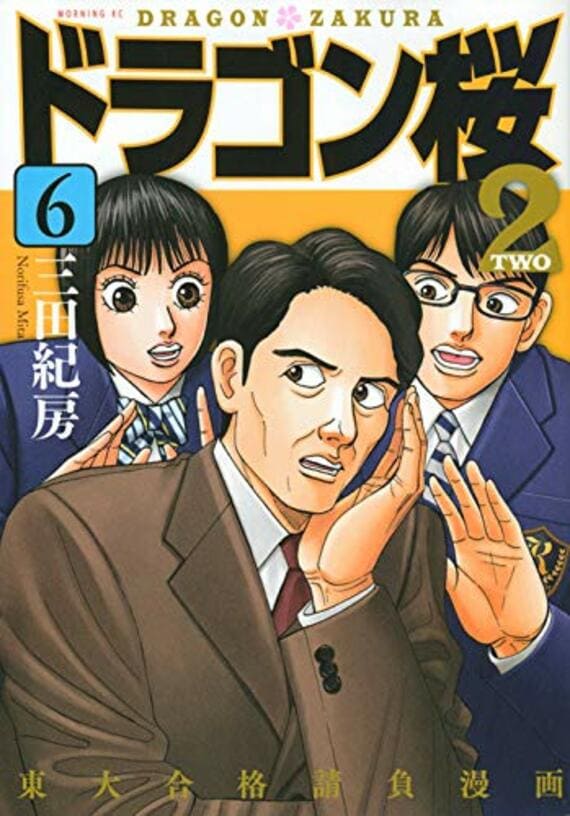































無料会員登録はこちら
ログインはこちら