一方で、訪ねる側の中にも「心ある人」が0.01%程度はいることは、経験からわかっています。つまり、1万人に1人くらいですね(笑)。
貴重な話を聞いたら、自分の地域に戻って実践を
そのような「心ある人」にはぜひとも心がけていただきたいのは、話を聞きに行って終わりではなく、小さくとも実践するという覚悟をもって行き、必ず自分の関係する現場に戻ったら実践することです。
そして、その成果を訪ねた地域の人に報告してほしいのです。何より、単に視察するだけではお金と時間の無駄遣いをしていて、自分のいる地元をさらに衰退たらしめることになっていることを認識しなくてはならないのです。無駄な視察ばかりしていては、活性化に近づいているどころか、逆に遠のいているのです。
実は、筆者も2003年、学生時代にアメリカ・ニューヨークのタイムズスクエアのマネジメントオフィスに訪ねたときに「日本人はよく来るのだが、話した内容がどう実践されたのか、全くフィードバックがない」ということを厳しく言われたことがあります。
日本人は国内だけでなく、海外でもそのような無責任な視察をしているのかと思ったのと同時に大変恥ずかしくもなりました。戻ってから自分の営んでいた事業会社で広告事業や、ビル管理合理化によるエリアマネジメントを立ち上げて今があるのも、そんな話に刺激を受けたからでした。
また早稲田商店会の時に環境まちづくりを視察に来られた、福岡市新天町の商店街さんは、同じように実践肌でした。視察から戻ってすぐに生ゴミ処理機を商店街で導入し、商店街内の飲食店から廃棄される生ゴミ処理を開始、地域の人々にできたコンポスト(堆肥)を配る取り組みを始められたりしました。こういう実践をすぐにする人たちの視察であれば大歓迎、むしろ実践する現場にも励みになります。
他の地域でその成功のプロセスを学ぶためには、成果をただ見に行っても仕方ありません。その人達がどのような紆余曲折を経て素晴らしい成果をあげたのか、幾度も訪れた危機を「どういう考え方で乗り越えたのか」といった根本的かつ論理的な考え方を聞けるかどうかです。また「どうしてそこから逃げなかったのか」という、ある意味ではメンタル的な生き方であったり、「どうして、今までにない発想ができたのか」という、生き方から学ぶことだったりするのです。
招かるざるヒマ人が来ないように、そして自分が他地域から招かれざるヒマ人にならぬようにすることが地域に活力を生み出す上でも大切なことでもあります。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

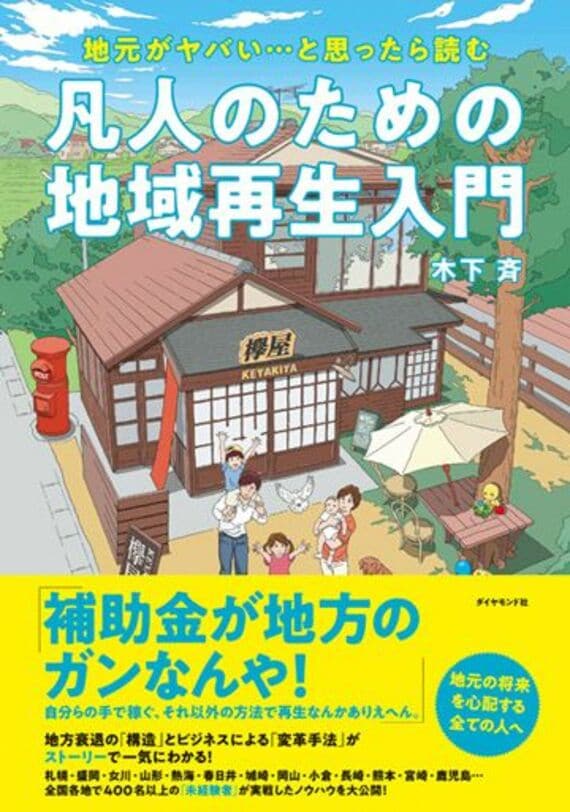































無料会員登録はこちら
ログインはこちら