この意味するところは、地球上の人口は約70億人なので、人間向けに携帯電話などの販売競争をすると70億回線がマックスだが、あらゆるモノがインターネットとつながるIoT(モノのインターネット)の時代は1兆回線まで市場が膨らむかもしれないということだ。
あらゆるモノがネットにつながるためには半導体がモノの中に組み込まれなければならない。デバイスがリアルタイムでつながることで、そこにビッグデータが誕生する。そのデータを使いこなしてこそ、あらゆるビジネスで競争優位に立てるというのが孫氏の描く戦略だ。
世界の自動車保有台数は約13億台とも言われる。孫氏はクルマを「デバイス」と位置付けることで、大きなビジネスチャンスが生まれると見ている。当面、クルマを「デバイス」として有効活用できるのが、移動のニーズとデマンドをマッチングさせるライドシェアなどの配車サービスと言えるだろう。ソフトバンクがアメリカのウーバーや中国の滴滴出行(DiDi)などに出資して筆頭株主となっているのは、こうした狙いからだ。
クルマの「デバイス化」とは、言い換えれば「クルマのスマートフォン化」でもある。スマホはネットワークの中で位置づけられて、ビッグデータを創出する源泉の一つとなるし、また、そのビッグデータを活用するための「利器」ともなる。さらに言えば、これからの時代はスマホとクルマが融合する時代になっていくのである。
トヨタもこうした流れを確実に受け止めてきた。
トヨタ車のユーザーとトヨタが「つながる」場所
名古屋市内にある高層ビルの一角に、メディアにはほとんど公開されていないトヨタのオフィスがある。入室の際には静脈認証を求められるほど厳しいセキュリティだ。子会社のトヨタコネクティッドが運営する「コネクティッドセンター」である。文字通り、専用カーナビやスマホを通じて、トヨタ車のユーザーとトヨタが「つながる」場所なのだ。「先読み情報サービス」という情報提供システムもあり、目的地の設定をしなくても、これまでの走行履歴から行き先や経路を予測して、事故・渋滞・天候・残燃料の案内が運転中、ナビ画面に表示される。
以前は高級車「レクサス」にのみ、こうしたサービスを受けられる専用端末が標準装備されていた。それが対応カーナビを装着すれば、レクサス以外の車でも、スマホなどを経由して音声認識システムでのサービスが受けられるようになった。顧客との対話記録を蓄積してビッグデータ化して検索に利用するという。トヨタによる「クルマのスマホ化」とも言える。

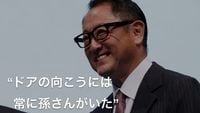






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら